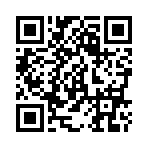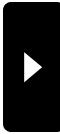2011年03月23日
茨城ホウレン草問題
http://onceinamillennium.tsukuba.ch/
怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒
東京電力社長のクソバカヤロウがぁ!!
出荷規制で売れなくなったホウレン草をたらふく食わせてやらぁ!!
口を開いて待っていやがれぇぇぇぇぇーっ!!!!
怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒
怒りの表明、これにて完了。
成り行きというか、茨城ホウレン草問題にも取り組むことになってしまった。
でも、このおちゃらけたブログで論じるには重大すぎる問題なんで、
↓こちらの真面目なブログのほうで色々書くから、どうぞよろしく。
http://onceinamillennium.tsukuba.ch/
怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒
東京電力社長のクソバカヤロウがぁ!!
出荷規制で売れなくなったホウレン草をたらふく食わせてやらぁ!!
口を開いて待っていやがれぇぇぇぇぇーっ!!!!
怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒 怒
怒りの表明、これにて完了。
成り行きというか、茨城ホウレン草問題にも取り組むことになってしまった。
でも、このおちゃらけたブログで論じるには重大すぎる問題なんで、
↓こちらの真面目なブログのほうで色々書くから、どうぞよろしく。
http://onceinamillennium.tsukuba.ch/
2011年03月21日
まさかこんなことを始めるとは思ってもいなかった
あ~俺はぁどうかしちまっただぁ~。
いきなりこんなこと始めちまっただよ~。
大地震と大津波と原発事故のせいでストレスたまりまくったせいか~?
それとも変な霊に取り付かれただかぁ~?
‥‥なんて言ってる場合じゃないぞ。
詳しいことはコレ見てくれ。↓
http://onceinamillennium.tsukuba.ch/
言っとくけど大地震でも起きなきゃこんなことやらんぞ。
いきなりこんなこと始めちまっただよ~。
大地震と大津波と原発事故のせいでストレスたまりまくったせいか~?
それとも変な霊に取り付かれただかぁ~?
‥‥なんて言ってる場合じゃないぞ。
詳しいことはコレ見てくれ。↓
http://onceinamillennium.tsukuba.ch/
言っとくけど大地震でも起きなきゃこんなことやらんぞ。
2011年03月21日
大地震が起きた
この文章は、ネットカフェの一室にこもって書いている。
3月11日、朝方にいつもの夜勤から帰宅し、午後やや遅くに目覚めた僕は、台所で家事をしながらこれからの外出予定のことを考えていた。
いきなり床が揺れだした。これまでにも地震は幾度か経験したことがあるが、この揺れはそれまでに経験したことのない激しさだ。危険を感じたので急いでドアを開けて外へ出た。
僕の部屋はアパートの2階。入り口すぐ近くの鉄製の手すりにつかまって、僕は周りの景色を見つめた。
周りの家がゆさゆさ揺れているのが一目で分かる。足元の揺れがあまりにも激しくて、「まるで遊園地のアトラクションみたいだ」と思った。不思議と恐怖感は感じなかったが、ただ自分の住む築ン十年は経っていそうなアパートが、激しい揺れで潰れないかどうかが心配だった。
しばらくして揺れは止み、台所に戻ってみると、棚の食器が落下してお気に入りの食器がいくつも砕けていた。重たい冷蔵庫は30センチほど動いてしまい、もともと散らかっていた自分の部屋はいっそう散らかってしまった。
やがて、同じアパートの住人が戻ってきた。しばらく前に越してきた、いい年したオヤジだ。
「すごかったな~、100円ショップにいたんだけど、揺れで棚の商品がみんな落っこちて、電気が通じなくなって追い出されちゃったよ」
「こっちも冷蔵庫が動いちゃいましたよ」
隣に住むおばあさんも外に出てきたので、オヤジは声をかけた。
「おばさん、大丈夫か?」
「うちの仏壇が倒れちゃって、一人では起こせないよ」
皆で笑いながらそんな会話を交わした後、オヤジはドアを開けてびっくり。
「うわ、こりゃひどいな」
「うちだって、そんなもんですよ」
オヤジとの会話を終えて僕は部屋へ戻る。やがて電気が回復し、先の地震のニュースをやっていないかと思ってテレビをつけた。
流れてきたのは信じられない映像だった。
町が濁流に飲み込まれ、船が町の中を流れていく。
幌のついた桟橋が押し流され、建物に衝突する。
車が次々と何十台も連なって流されていく。
黒い水とそれに押し流される建物の残骸が大地を覆い、田畑を飲み込んでいく。
この時になって僕は、ようやくこの震災の深刻さを知った。
3月11日、朝方にいつもの夜勤から帰宅し、午後やや遅くに目覚めた僕は、台所で家事をしながらこれからの外出予定のことを考えていた。
いきなり床が揺れだした。これまでにも地震は幾度か経験したことがあるが、この揺れはそれまでに経験したことのない激しさだ。危険を感じたので急いでドアを開けて外へ出た。
僕の部屋はアパートの2階。入り口すぐ近くの鉄製の手すりにつかまって、僕は周りの景色を見つめた。
周りの家がゆさゆさ揺れているのが一目で分かる。足元の揺れがあまりにも激しくて、「まるで遊園地のアトラクションみたいだ」と思った。不思議と恐怖感は感じなかったが、ただ自分の住む築ン十年は経っていそうなアパートが、激しい揺れで潰れないかどうかが心配だった。
しばらくして揺れは止み、台所に戻ってみると、棚の食器が落下してお気に入りの食器がいくつも砕けていた。重たい冷蔵庫は30センチほど動いてしまい、もともと散らかっていた自分の部屋はいっそう散らかってしまった。
やがて、同じアパートの住人が戻ってきた。しばらく前に越してきた、いい年したオヤジだ。
「すごかったな~、100円ショップにいたんだけど、揺れで棚の商品がみんな落っこちて、電気が通じなくなって追い出されちゃったよ」
「こっちも冷蔵庫が動いちゃいましたよ」
隣に住むおばあさんも外に出てきたので、オヤジは声をかけた。
「おばさん、大丈夫か?」
「うちの仏壇が倒れちゃって、一人では起こせないよ」
皆で笑いながらそんな会話を交わした後、オヤジはドアを開けてびっくり。
「うわ、こりゃひどいな」
「うちだって、そんなもんですよ」
オヤジとの会話を終えて僕は部屋へ戻る。やがて電気が回復し、先の地震のニュースをやっていないかと思ってテレビをつけた。
流れてきたのは信じられない映像だった。
町が濁流に飲み込まれ、船が町の中を流れていく。
幌のついた桟橋が押し流され、建物に衝突する。
車が次々と何十台も連なって流されていく。
黒い水とそれに押し流される建物の残骸が大地を覆い、田畑を飲み込んでいく。
この時になって僕は、ようやくこの震災の深刻さを知った。
2011年03月21日
日記再開します
すみません。2月8日以来、色々と忙しくなって、東京で見つけた仕事もけっこう大変で、通勤時間もやたらと長いものだから、ずっと日記つけるのサボってました。3月になって、いい加減に日記を再開しようと思っていたんですが、そしたら3月11日の午後に大地震が起きてしまいました。
大丈夫です、生きてます。茨城県は被災県だけど、私の住む茨城県南は地震の被害も軽かったし、電気と水の心配もありません。大地震で仕事を失うこともなかったし、今では職場のある東京まで通う列車も運行しています。
でも‥‥それまでの人生が大地震でばっさり断ち切られて、別の人生に放り込まれてしまったような。大地震がなければ、今頃は3月下旬に水戸芸術館で開かれる水戸子供演劇アカデミーの公演を観に行くのを、楽しみにしていたはずなんですが。
現在、水戸芸術館は地震の被害で閉館となり、茨城県南から水戸へ向かう常磐線の路線も復旧していません。
ともあれ、今日より日記を再開します。
大丈夫です、生きてます。茨城県は被災県だけど、私の住む茨城県南は地震の被害も軽かったし、電気と水の心配もありません。大地震で仕事を失うこともなかったし、今では職場のある東京まで通う列車も運行しています。
でも‥‥それまでの人生が大地震でばっさり断ち切られて、別の人生に放り込まれてしまったような。大地震がなければ、今頃は3月下旬に水戸芸術館で開かれる水戸子供演劇アカデミーの公演を観に行くのを、楽しみにしていたはずなんですが。
現在、水戸芸術館は地震の被害で閉館となり、茨城県南から水戸へ向かう常磐線の路線も復旧していません。
ともあれ、今日より日記を再開します。
2011年03月21日
ダンスフェスティバル2011(2月末頃に書いた文章)
このところ、夜勤明けの給料日にお給料が入って真っ先にやることは、某ファミレスの朝食バイキングでひたすら食いまくることになっちまった。現在も生活再建中で自宅のパソコンからネットにアクセスできず、ネットカフェからブログにカキコする状況がまだまだ続きそうなのは仕方ない。とりあえず、過去に書いておいた文章をUP。土浦で開催されたバレエイベントを観に行った時の報告だ。
土浦石岡地方 ダンスフェスティバル2011
日時 平成23年2月13日(日)
13:00 開演 入場無料
会場 土浦市亀城プラザ文化ホール
主催 土浦市亀城プラザ広域利用推進委員会
土浦石岡地方広域市町村圏協議会
土浦市亀城プラザ
新聞に折り込みの地元情報誌で情報を漁っていて、13日にこのイベントをやることを知ったのが当日の夜明け前。その出場団体の中に萩谷京子現代舞踏研究所の名前を見つけて、観に行くことに決めた。
萩谷京子現代舞踏研究所とはちょっとした縁がある。自分は昨年の秋、水戸芸術館で開催された『ドン・キホーテ』にチョイ役で参加したけれど、その劇中でダンスを披露したのがかの舞踏研究所なのだ。『ドン・キホーテ』の時、自分も役者の1人だったから、折角のハイレベルなダンスも控え室のモニターを通してとか、舞台の隅から覗き見するくらいしか出来なかったのが残念だったが、今回はお客の1人として客席から堂々と観ることが出来てとても満足だった。
地元のダンスグループ5団体が出演するこのイベントは、初心者からプロ級までさまざまなレベルのダンサーがダンスを披露する構成になっていて、ステージに立った人数をプログラム掲載の名簿で数えてみたら、200人を越えている。ダンスの内容も童話『マッチ売りの少女』を題材にしたり、森の中の情景をイメージしたり、「サラリーマンのお父さん頑張れ!」のノリノリな歌に合わせてスーツ姿で踊ったりとか、「赤ちゃん抱いたママさん集まれ!」って感じでダンスしちゃうのとか、ネコ耳つけたニャンコ風の踊りとか、色々あって楽しめた。その中でも萩谷京子現代舞踏研究所の見せてくれたダンスは。
いや、なんかもう。
圧倒されちゃったよ。
だって高校生くらいの女の子が、舞台の袖から走ってくるなり、いきなり空中で横転ジャンプ決めちゃうんだから。
え? 今の何?
‥‥一瞬、見たものが信じられなかった。
足が上、頭が下の姿勢で、空中に浮いちゃってるよ。
俺には絶対、真似できねぇ~。
下手に真似したら絶対、首の骨折るぞ~。
それにダンスの最中、舞台に立った総勢十何人かのティーンっぽい女の子達が、横転しながらコロコロ転がっていくシーンがあったりして。なんでみんなしてあんなにコロコロ転がれるんだ? でもそんなのは序の口で、続いて登場したどう見立って幼稚園児にしか見えないちっちゃな女の子達が、フリフリのダンス衣装着たその姿でコロコロコロコロ横転で転がっていくのにはもう。驚きました。未だに見た物が信じられません。
いや~、凄いもの見せてもらっちゃぃましたよ。
次に公演ある時にも、ぜひぜひ観に行きたいです。
注:この文章は3月11日に発生した、東日本巨大地震の発生前に書かれました。
土浦石岡地方 ダンスフェスティバル2011
日時 平成23年2月13日(日)
13:00 開演 入場無料
会場 土浦市亀城プラザ文化ホール
主催 土浦市亀城プラザ広域利用推進委員会
土浦石岡地方広域市町村圏協議会
土浦市亀城プラザ
新聞に折り込みの地元情報誌で情報を漁っていて、13日にこのイベントをやることを知ったのが当日の夜明け前。その出場団体の中に萩谷京子現代舞踏研究所の名前を見つけて、観に行くことに決めた。
萩谷京子現代舞踏研究所とはちょっとした縁がある。自分は昨年の秋、水戸芸術館で開催された『ドン・キホーテ』にチョイ役で参加したけれど、その劇中でダンスを披露したのがかの舞踏研究所なのだ。『ドン・キホーテ』の時、自分も役者の1人だったから、折角のハイレベルなダンスも控え室のモニターを通してとか、舞台の隅から覗き見するくらいしか出来なかったのが残念だったが、今回はお客の1人として客席から堂々と観ることが出来てとても満足だった。
地元のダンスグループ5団体が出演するこのイベントは、初心者からプロ級までさまざまなレベルのダンサーがダンスを披露する構成になっていて、ステージに立った人数をプログラム掲載の名簿で数えてみたら、200人を越えている。ダンスの内容も童話『マッチ売りの少女』を題材にしたり、森の中の情景をイメージしたり、「サラリーマンのお父さん頑張れ!」のノリノリな歌に合わせてスーツ姿で踊ったりとか、「赤ちゃん抱いたママさん集まれ!」って感じでダンスしちゃうのとか、ネコ耳つけたニャンコ風の踊りとか、色々あって楽しめた。その中でも萩谷京子現代舞踏研究所の見せてくれたダンスは。
いや、なんかもう。
圧倒されちゃったよ。
だって高校生くらいの女の子が、舞台の袖から走ってくるなり、いきなり空中で横転ジャンプ決めちゃうんだから。
え? 今の何?
‥‥一瞬、見たものが信じられなかった。
足が上、頭が下の姿勢で、空中に浮いちゃってるよ。
俺には絶対、真似できねぇ~。
下手に真似したら絶対、首の骨折るぞ~。
それにダンスの最中、舞台に立った総勢十何人かのティーンっぽい女の子達が、横転しながらコロコロ転がっていくシーンがあったりして。なんでみんなしてあんなにコロコロ転がれるんだ? でもそんなのは序の口で、続いて登場したどう見立って幼稚園児にしか見えないちっちゃな女の子達が、フリフリのダンス衣装着たその姿でコロコロコロコロ横転で転がっていくのにはもう。驚きました。未だに見た物が信じられません。
いや~、凄いもの見せてもらっちゃぃましたよ。
次に公演ある時にも、ぜひぜひ観に行きたいです。
注:この文章は3月11日に発生した、東日本巨大地震の発生前に書かれました。
2011年02月08日
観劇『ライフ・イン・ザ・シアター』at水戸芸術館
去る2月6日、水戸まで行って観劇した『ライフ・イン・ザ・シアター』のことを書こう。
この劇のテーマは役者人生。しかも舞台に立つ役者はたったの2人。まあ、役者の着替えを手伝ったり、道具を運んだりする劇場スタッフも何人か舞台の上に姿を見せるのだけれど、役者として演技を見せるのは実質的に2人だ。シナリオを書いたのはアメリカの劇作家、ディヴィッド・マメット。1976年のシカゴが初演で、日本では1997年に東京で上演されているけれど、水戸で上演するのは初めてらしい。
上演時間は約2時間。その長い時間をたった2人の役者で持たせてしまうのだから凄い。役者がたった2人の劇だと知って、観ていて退屈するかもしれないと最初は思っていたけれど、全然そんなことはなかった。テンポが良くて、場面の切り替えが何度も何度もあって、あれよあれよという間に話が進んでいく。パンフレットによると場の数は26場。役者2人が控え室で着替えていたと思ったら、次の瞬間には観客の前に立っていて、その次の瞬間には着替え室に戻ってセリフの稽古をしていたり、またまた次の瞬間には劇場から出ていきながら「これから飲みに行こうぜ~」なんて話をしている。
いやまさに光陰矢のごとし、というか。舞台の表と裏を駆け巡る役者人生を見事に表しているというか‥‥。
実は私、水戸演劇学校の卒業公演やリージョナルシアターの公演に参加して、水戸芸術館の舞台にも発った経験があるんで、あの世界の雰囲気を肌で感じていた時期がある。だからこの芝居を観て、舞台で演じられていることをあまりにもリアルに感じすぎてしまい、なんだか気恥ずかしいような妙な気分になった。ことに男性控え室の野郎臭い雰囲気が良く出ていたとは思ったけど、年老いてまるで元気なさそうな爺さんの役をやったロバートが控え室に戻ってくるなり、「この毛布もっとよく洗っとけ! 体育館みたいな臭いだぞ!」って怒鳴るシーン、うわ~あのセリフ、オレ的にハマりすぎだよ。あるんだよな~ああいうことって。
あと面白いと思ったのは、セットの凝り方。設定上、役者が客席側に背中を向けて演技をすることが多いせいか、舞台の背景が鏡張りになっている。客席に背中を向けても役者の顔は鏡に映るから、客席からは鏡を通して表側から舞台を観ることが出来る。また鏡に映る暗い客席を、空っぽの客席に見立てて役者が芝居をしたりする。特に救命ボートで海をさすらうシーン、舞台の表と裏がよく分かる見せ方で、見事だった。
舞台の後半からは俳優として上り坂の人生を歩んでいくジョンと、年老いて人生下り坂になっていくロバートの対比が際立って、シリアスな雰囲気になっていく。でも、ラストは意外とあっけなかった。「え、これで終わりなの?」という感じがした。2人の物語はまだまだ続いていくのだけれど、区切りのいいところで「はい、おしまい」という、ラストらしからぬラスト。ラストで大いに盛り上がる芝居を見慣れてきた目からは、シラッとした感じがするけれど、私としてはあのラストの雰囲気が、最後の公演を終えて舞台の熱狂が冷めた後に残るシラッとした雰囲気を連想させて、いい味を出しているようにも思えた。あれも役者人生の一コマ。
2011年02月06日
どうやらオレは酸素欠乏症にかかったらしい
ほら酸素欠乏症っていったらアレだよアレ、機動戦士ガンダムでアムロ君のお父ちゃんがかかっちゃったヤツだ。酸素が足りなくなって脳細胞が大量死するか何かして、マトモな思考ができなくなるビョーキだよ。スクラップの電化製品からかき集めたガラクタのパーツでワケのわかんない装置を作って、これがガンダムのパワーアップアイテムだ、とか何とか言っちゃったりして。これが酸素欠乏症にかかったガンダム開発者の成れの果て。
「父さんは酸素欠乏症に‥‥‥‥うああああああああああーっ 」
」
‥‥と、そっちの話はひとまず置いといて。
その酸素欠乏症にどうやらオレもかかっちまったようだぜ。最近、脳ミソが死んでるっぽくって、気がついたら丸一日寝てたとか、文章書けなくなってブログほったらかしとか、仕事帰りに乗った山手線で寝込んじまって気がついたら2周してたとか。考えてみるとストレスたまる生活続けてたし、食費切り詰めすぎて脳の栄養足りなかったっぽいし、それに問題なのは日ごろの体の姿勢だ。呼吸法でよく言われてることだけど、姿勢が悪いと肺が十分な酸素を取り込めないで、脳の働きが悪くなる。何も考えられないでぼーっと過ごすことが多くなる。無気力になって何もかもが面倒くさくなる。というのが今のオレの状態そのもの。こりゃヤバいと思い、呼吸法を改善しようと考えて、全身使って呼吸をするようにしてみた。背筋をまっすぐに伸ばして、腹式呼吸と胸式呼吸を同時進行させて腹と胸でスーハースーハー‥‥やってたら全身筋肉痛になりやがった、ぢぐじょー何でこうなる?
それはそうと、今日は水戸まで芝居を観に行った。水戸芸術館のACM劇場で公演の『ライフ・イン・ザ・シアター』、今年初めて観る水戸の芝居だ。役者人生をテーマにした芝居、面白かった。役者はたったの2人なのに、よくあれだけの時間持たせられるなと感心した。でも水戸の演劇学校とかリージョナルシアターに役者の一人として参加したオレからすると、舞台の上で役者が演じる話があまりにも身近に感じられすぎて、何だか気恥ずかしいよーな。
で、今のオレは水戸の芝居を観に行った帰り、かすみがうら市と土浦市の境あたりにあるネットカフェでコーヒー飲みながら、キーボード叩いてブログに文章打ち込んでるとこだ。このネカフェはオープン席が3時間パックで500円だから、のんびりできるぜ。
そういえばクリスマス以来、いろいろ芝居を観てきたよな。
去年のクリスマス・イブに観たのが劇団SCOTの『ディオニュソス』、
クリスマス当日に観たのが、劇団キミトジャグジーの『GrinningGhosts!〜666番街の幸せな悪夢〜』、
年明けて、1月29日に観たのが百景社の『人形の家』、
翌1月30日に観たのが新宿梁山泊の『風のほこり』、
そして今日、2月6日に観てきたのが水戸ACM劇場の『ライフ・イン・ザ・シアター』。
こんなに観て来たのに、劇のことを書こう書こうと思いながらも、脳ミソ働かなくって書けずじまいになっていた。とりあえず今夜あたり、時間がある時に書いておこうかな。‥‥また酸素欠乏症の症状でなきゃいいけど。
「父さんは酸素欠乏症に‥‥‥‥うああああああああああーっ
 」
」‥‥と、そっちの話はひとまず置いといて。
その酸素欠乏症にどうやらオレもかかっちまったようだぜ。最近、脳ミソが死んでるっぽくって、気がついたら丸一日寝てたとか、文章書けなくなってブログほったらかしとか、仕事帰りに乗った山手線で寝込んじまって気がついたら2周してたとか。考えてみるとストレスたまる生活続けてたし、食費切り詰めすぎて脳の栄養足りなかったっぽいし、それに問題なのは日ごろの体の姿勢だ。呼吸法でよく言われてることだけど、姿勢が悪いと肺が十分な酸素を取り込めないで、脳の働きが悪くなる。何も考えられないでぼーっと過ごすことが多くなる。無気力になって何もかもが面倒くさくなる。というのが今のオレの状態そのもの。こりゃヤバいと思い、呼吸法を改善しようと考えて、全身使って呼吸をするようにしてみた。背筋をまっすぐに伸ばして、腹式呼吸と胸式呼吸を同時進行させて腹と胸でスーハースーハー‥‥やってたら全身筋肉痛になりやがった、ぢぐじょー何でこうなる?
それはそうと、今日は水戸まで芝居を観に行った。水戸芸術館のACM劇場で公演の『ライフ・イン・ザ・シアター』、今年初めて観る水戸の芝居だ。役者人生をテーマにした芝居、面白かった。役者はたったの2人なのに、よくあれだけの時間持たせられるなと感心した。でも水戸の演劇学校とかリージョナルシアターに役者の一人として参加したオレからすると、舞台の上で役者が演じる話があまりにも身近に感じられすぎて、何だか気恥ずかしいよーな。
で、今のオレは水戸の芝居を観に行った帰り、かすみがうら市と土浦市の境あたりにあるネットカフェでコーヒー飲みながら、キーボード叩いてブログに文章打ち込んでるとこだ。このネカフェはオープン席が3時間パックで500円だから、のんびりできるぜ。
そういえばクリスマス以来、いろいろ芝居を観てきたよな。
去年のクリスマス・イブに観たのが劇団SCOTの『ディオニュソス』、
クリスマス当日に観たのが、劇団キミトジャグジーの『GrinningGhosts!〜666番街の幸せな悪夢〜』、
年明けて、1月29日に観たのが百景社の『人形の家』、
翌1月30日に観たのが新宿梁山泊の『風のほこり』、
そして今日、2月6日に観てきたのが水戸ACM劇場の『ライフ・イン・ザ・シアター』。
こんなに観て来たのに、劇のことを書こう書こうと思いながらも、脳ミソ働かなくって書けずじまいになっていた。とりあえず今夜あたり、時間がある時に書いておこうかな。‥‥また酸素欠乏症の症状でなきゃいいけど。
2011年01月03日
初夢
正月のいつに見た夢を初夢とするかには、色々と説が分かれているようだ。
初日の出を拝む前に見た夢を初夢とする説もあるようだし、正月を迎えたその晩に見た夢を初夢とする説もあるようだ。
俺もこの1月1日の昼間、自宅で寝入っているうちに夢らしきものを見た覚えがある。が、残念ながらその内容を覚えていない。
でも1月1日の夜、初詣からの帰りにネットカフェに泊まり、そこで寝入って見た夢なら覚えている。とりあえずその夢を初夢ということにしておこう。
それはこんな夢だ。
そこは幽霊屋敷みたいな暗い夜の屋敷の中。妖怪でも出そうな雰囲気の中、誰かさんと一緒に片付け物をしながら、邪気を払うように踊っていた。昔、妖怪図鑑か何かで見た怖いヤツが出てくるんじゃないかな~と思いながらも、自然生の田楽舞いみたいな感じで踊っていた。そんな夢だ。
初夢の次に見た夢も覚えている。亀と金魚の夢だ。
俺は夢の中で、どこかのおじさんと一緒に夜中のプールのお掃除をしていたようなのだが、明るい照明に照らされたプールの水というのが、野菜とかいっぱい浮かんでいるスープみたいで、野菜と野菜の合間に亀や金魚がぐた~っとなって浮いている。死んでるのかと思って突っついてみたら動くので生きていると分かった。そんな夢だ。
これが富士山か鷹かナスビの夢なら、間違いなくおめでたい夢なんだろうが、亀と金魚はどうなんだ? しかも初夢の次に見た夢。亀も金魚も縁起物だとは思うんだが。
とりあえず以前にネットで知った、自称・怪しい霊能者さんにでも相談してみよか。
初日の出を拝む前に見た夢を初夢とする説もあるようだし、正月を迎えたその晩に見た夢を初夢とする説もあるようだ。
俺もこの1月1日の昼間、自宅で寝入っているうちに夢らしきものを見た覚えがある。が、残念ながらその内容を覚えていない。
でも1月1日の夜、初詣からの帰りにネットカフェに泊まり、そこで寝入って見た夢なら覚えている。とりあえずその夢を初夢ということにしておこう。
それはこんな夢だ。
そこは幽霊屋敷みたいな暗い夜の屋敷の中。妖怪でも出そうな雰囲気の中、誰かさんと一緒に片付け物をしながら、邪気を払うように踊っていた。昔、妖怪図鑑か何かで見た怖いヤツが出てくるんじゃないかな~と思いながらも、自然生の田楽舞いみたいな感じで踊っていた。そんな夢だ。
初夢の次に見た夢も覚えている。亀と金魚の夢だ。
俺は夢の中で、どこかのおじさんと一緒に夜中のプールのお掃除をしていたようなのだが、明るい照明に照らされたプールの水というのが、野菜とかいっぱい浮かんでいるスープみたいで、野菜と野菜の合間に亀や金魚がぐた~っとなって浮いている。死んでるのかと思って突っついてみたら動くので生きていると分かった。そんな夢だ。
これが富士山か鷹かナスビの夢なら、間違いなくおめでたい夢なんだろうが、亀と金魚はどうなんだ? しかも初夢の次に見た夢。亀も金魚も縁起物だとは思うんだが。
とりあえず以前にネットで知った、自称・怪しい霊能者さんにでも相談してみよか。
2011年01月03日
初参り
今年の初詣、神社巡りで筑波山神社に行こうと決めていた。去年と一昨年は遠くの川崎大師までお参りに行ったのだが、この年末年始も不景気が続いているし、俺も長期失業の後の生活再建中で予算が乏しいし、川崎チッタデラとかでのカウントダウンと年明けイベントの大騒ぎに付き合うような気分でもないし。それで結局、今回は地元の神社にお参りして済まそうと決めた。地元といっても筑波山の麓までは自転車で片道2時間半、いやもっとかかるかな?
そしてもう一社、筑波山の麓にある蚕影山神社にもお参りしようとも決めていた。こちらの神社それほど有名ではなさそうだけれど、筑波に伝わる金色姫伝説ゆかりの神社で養蚕の守り神。この伝説を知ってから、いつかお参りしようと思っていたのだ。
でも正月で昼間は人が多そうだし、列に並んで延々と待たされるのは嫌なんで(一昨年の川崎大師で懲りた)、人の少なくなりそうな夕方狙い。で、昼間はカラオケとかで時間潰して、午後も遅くなってから自転車で筑波山を目指したら、予想外に時間がかかっちまった。しかも冬場は暗くなるのが早い。気がついたら夕暮れ時、自転車で走ってるうちに日が沈んで、どんどん暗くなっていく。

こりゃまずいよ~、初参りのはずが真夜中の丑の刻(うしのこく)参りになっちまうよ~。え、知らない? 丑の刻参りってのは、丑の刻すなわち夜の午前1時から3時の時間に白装束で神社へ出かけて、ご神木に呪いの藁人形を五寸釘でガンガン打ちつけて、憎いヤツを呪い殺す日本の伝統行事‥‥でもないか。とかおバカなことを考えながら走ってるうちに、運良く道案内の案内図を見つけた。やったぞ、これで蚕影山神社まで道に迷わずに済むぞ。

そういえば蚕影山神社の神様は蚕の守り神。蚕といえば怪獣モスラのモデルになった昆虫だ。モスラだって映画の中で糸吐いて繭作るし、そいえばマスコットの小美人の姉妹がモスラの歌とか歌ってたよな~。いつか蚕影山神社でモスラの歌を歌いながらコスプレの奉納舞を踊ってやろか? なんて相変わらずおバカなことを考えつつ、蚕影山神社に着いた時には日はすっかり暮れて、西の空に少しばかりの残光が残るのみ。その微かな光に照らされて、神社の入り口に立つ白地の看板が見える。『蚕影山神社 入口』と。
参道は石段になっていて、外灯も何もついてないから真っ暗。なんかヤバそうな雰囲気だと思ったけど、折角ここまで来たのだしと思い、俺はその石段を昇り始めた。途中に小さな鳥居があって、注連縄に付けられた紙垂(しで)が頭に触れそうな程に低く垂れ下がっている。その鳥居をくぐるとまた石段が延々と。俺は日没後の微かな残光を頼りに石段を登り続けた。──正月でもなけりゃこんなことはやらんぞ──。そしてついにたどり着いた。神社の本殿の正面に。当然ながらここも真っ暗。
賽銭箱に御賽銭を入れ、参拝して帰路につく。
帰り道、慎重な足取りで石段を下りながら、「罰当たりモンはこういう時に石段から転げ落ちて大怪我するんだよな」とか考えた。が、別に途中で転ぶこともなく、無事に境内から出ることが出来た。
蚕影山神社でお参りした後、筑波山神社へは登山道を通って行った。自転車は手頃な道端に停め、両側に民家の立ち並ぶ登山道を徒歩で歩き始める。道脇の立て札を見ると、『筑波山神社まで2km』。坂道はだんだん急になる。道行く人は俺以外にはおらず、ただ1人、地元の人とおぼしき女性とすれ違ったのみ。辺りの民家はなぜか明かりの灯っていない家が多い。夜が早いから早々に寝入ってしまったのか、それとも正月休みは他所に出かけているのか? 時計を見るとまだ午後の6時前だ。途中、坂道の上の方から車が走ってきたり。車を停めてある民家も多い。こんな20~30度の勾配がありそうな坂を、よく車で走れるなと感心する。
やっと赤い大鳥居の場所までたどり着くと、筑波山神社はそこからすぐの場所だった。山地で土地が狭いせいか、御神橋の回りや神社の本殿に向かう石段の両脇にも、屋台がずらりと並んでいる。少し離れた場所には土産物屋がひしめいているから、全体的に雑多で窮屈な感じがした。ま、仕方ないか。しかし本殿への入り口近くにある御神橋、俺がまだ体の小さな小学生だった頃、学校の遠足で見た時には大きな橋だと思ったのに、大人になった今ではこじんまりした橋に見える。屋台や土産物屋の並ぶ場所だって、あの頃はもっと広々と感じたものだ。

着いた時刻は午後6時半くらいだったろうか? それでもまだかなりの列が出来ていたが、そう待たされることもなく列は進んで行く。本殿の前の門には2人の武人の像が仁王像のように並んでいる。甲冑のデザインは平安・鎌倉時代あたりのもののようだが、中国の兵馬俑のような印象も受ける。後で像の由来を調べてみよう。

俺のすぐ近くには若いカップルがいて、本殿に飾ってある大きな鈴を見て、「ドラエモンみたいだね」とか話している。そのうちに「神様に何をお願いしようか? 願い事は3つまでかな?」なんて話をし出した。
願い事か。俺の場合、願いたいことは色々あるけどね。
東海村原発がメルトダウンしませんように、とか。
浜岡原発の真下で活断層がぶっちぎれませんように、とか。
どっかのバカな企業が今は亡きJCOみたいに、バケツに核燃料ぶちこんでひっかき回して臨界越えさせて中性子線を大量放出させちゃうような、バカな核事故を起こしませんように、とか‥‥。
書いていくとキリがないからやめる。いちいち願い事なんかしていたらキリがない。で、俺はいつも神社のお参りでそうしているように、願い事なんか一切せずに、二礼二拍一礼の挨拶だけして早々と退散した。その後で御神籤引いたら、なんと。
<<<<<大吉>>>>>
『冬の枯木に春が来て花さき黒雲晴れて月てり輝く如く次第に運開けて幸福加わり家業繁盛します』
やったね!! こりゃあ春から縁起がいいわ!!
あ、でも続いてこう書いてある。
『しかし安心して油断すると折角の幸が禍(わざわい)となります用心しなさい』
こ、こわ~っ!!!! こりゃ来年の正月まで気が抜けんな~
そしてもう一社、筑波山の麓にある蚕影山神社にもお参りしようとも決めていた。こちらの神社それほど有名ではなさそうだけれど、筑波に伝わる金色姫伝説ゆかりの神社で養蚕の守り神。この伝説を知ってから、いつかお参りしようと思っていたのだ。
でも正月で昼間は人が多そうだし、列に並んで延々と待たされるのは嫌なんで(一昨年の川崎大師で懲りた)、人の少なくなりそうな夕方狙い。で、昼間はカラオケとかで時間潰して、午後も遅くなってから自転車で筑波山を目指したら、予想外に時間がかかっちまった。しかも冬場は暗くなるのが早い。気がついたら夕暮れ時、自転車で走ってるうちに日が沈んで、どんどん暗くなっていく。
こりゃまずいよ~、初参りのはずが真夜中の丑の刻(うしのこく)参りになっちまうよ~。え、知らない? 丑の刻参りってのは、丑の刻すなわち夜の午前1時から3時の時間に白装束で神社へ出かけて、ご神木に呪いの藁人形を五寸釘でガンガン打ちつけて、憎いヤツを呪い殺す日本の伝統行事‥‥でもないか。とかおバカなことを考えながら走ってるうちに、運良く道案内の案内図を見つけた。やったぞ、これで蚕影山神社まで道に迷わずに済むぞ。
そういえば蚕影山神社の神様は蚕の守り神。蚕といえば怪獣モスラのモデルになった昆虫だ。モスラだって映画の中で糸吐いて繭作るし、そいえばマスコットの小美人の姉妹がモスラの歌とか歌ってたよな~。いつか蚕影山神社でモスラの歌を歌いながらコスプレの奉納舞を踊ってやろか? なんて相変わらずおバカなことを考えつつ、蚕影山神社に着いた時には日はすっかり暮れて、西の空に少しばかりの残光が残るのみ。その微かな光に照らされて、神社の入り口に立つ白地の看板が見える。『蚕影山神社 入口』と。
参道は石段になっていて、外灯も何もついてないから真っ暗。なんかヤバそうな雰囲気だと思ったけど、折角ここまで来たのだしと思い、俺はその石段を昇り始めた。途中に小さな鳥居があって、注連縄に付けられた紙垂(しで)が頭に触れそうな程に低く垂れ下がっている。その鳥居をくぐるとまた石段が延々と。俺は日没後の微かな残光を頼りに石段を登り続けた。──正月でもなけりゃこんなことはやらんぞ──。そしてついにたどり着いた。神社の本殿の正面に。当然ながらここも真っ暗。
賽銭箱に御賽銭を入れ、参拝して帰路につく。
帰り道、慎重な足取りで石段を下りながら、「罰当たりモンはこういう時に石段から転げ落ちて大怪我するんだよな」とか考えた。が、別に途中で転ぶこともなく、無事に境内から出ることが出来た。
蚕影山神社でお参りした後、筑波山神社へは登山道を通って行った。自転車は手頃な道端に停め、両側に民家の立ち並ぶ登山道を徒歩で歩き始める。道脇の立て札を見ると、『筑波山神社まで2km』。坂道はだんだん急になる。道行く人は俺以外にはおらず、ただ1人、地元の人とおぼしき女性とすれ違ったのみ。辺りの民家はなぜか明かりの灯っていない家が多い。夜が早いから早々に寝入ってしまったのか、それとも正月休みは他所に出かけているのか? 時計を見るとまだ午後の6時前だ。途中、坂道の上の方から車が走ってきたり。車を停めてある民家も多い。こんな20~30度の勾配がありそうな坂を、よく車で走れるなと感心する。
やっと赤い大鳥居の場所までたどり着くと、筑波山神社はそこからすぐの場所だった。山地で土地が狭いせいか、御神橋の回りや神社の本殿に向かう石段の両脇にも、屋台がずらりと並んでいる。少し離れた場所には土産物屋がひしめいているから、全体的に雑多で窮屈な感じがした。ま、仕方ないか。しかし本殿への入り口近くにある御神橋、俺がまだ体の小さな小学生だった頃、学校の遠足で見た時には大きな橋だと思ったのに、大人になった今ではこじんまりした橋に見える。屋台や土産物屋の並ぶ場所だって、あの頃はもっと広々と感じたものだ。
着いた時刻は午後6時半くらいだったろうか? それでもまだかなりの列が出来ていたが、そう待たされることもなく列は進んで行く。本殿の前の門には2人の武人の像が仁王像のように並んでいる。甲冑のデザインは平安・鎌倉時代あたりのもののようだが、中国の兵馬俑のような印象も受ける。後で像の由来を調べてみよう。
俺のすぐ近くには若いカップルがいて、本殿に飾ってある大きな鈴を見て、「ドラエモンみたいだね」とか話している。そのうちに「神様に何をお願いしようか? 願い事は3つまでかな?」なんて話をし出した。
願い事か。俺の場合、願いたいことは色々あるけどね。
東海村原発がメルトダウンしませんように、とか。
浜岡原発の真下で活断層がぶっちぎれませんように、とか。
どっかのバカな企業が今は亡きJCOみたいに、バケツに核燃料ぶちこんでひっかき回して臨界越えさせて中性子線を大量放出させちゃうような、バカな核事故を起こしませんように、とか‥‥。
書いていくとキリがないからやめる。いちいち願い事なんかしていたらキリがない。で、俺はいつも神社のお参りでそうしているように、願い事なんか一切せずに、二礼二拍一礼の挨拶だけして早々と退散した。その後で御神籤引いたら、なんと。
<<<<<大吉>>>>>
『冬の枯木に春が来て花さき黒雲晴れて月てり輝く如く次第に運開けて幸福加わり家業繁盛します』
やったね!! こりゃあ春から縁起がいいわ!!
あ、でも続いてこう書いてある。
『しかし安心して油断すると折角の幸が禍(わざわい)となります用心しなさい』
こ、こわ~っ!!!! こりゃ来年の正月まで気が抜けんな~
2011年01月03日
転載:どんぐりの家
>別ブログ、2010年11月25日の記事を転載。
http://ayayukimeia.tsukuba.ch/e104142.html
自然生クラブ、これは筑波山の麓にある、知的障害児と共に暮らす共同体だ。
一般的には障害児のための"施設"という呼ばれ方をするのだろうけれど、責任者の柳瀬氏はあえて"共同体"という言葉を使っておられるようだ。実際、自然生クラブの運営方針はユニークで、単に障害児の世話をするのみならず、障害児と共に有機農業を営み、また障害児と共に田楽舞という舞踏を嗜み、国内そして国外でもたびたび公演を行っている。また自然生クラブの職員を中心に結成された百景社という劇団があり、クラブの所有する劇場もある。この劇場はもともとは米を貯蔵する蔵だったものを改造したもので、百景社の公演に使われる以外にも、地元のアーティストの公演に貸し出されたり、また福祉や有機農業の分野で活躍する専門家がここに招かれ、セミナーが開かれたりすることもある。
その活動範囲は単なる施設の枠を越え、さまざまな人々のつながる共同体として機能している。だから私も"施設"よりも"共同体"という呼び名の方が相応しいと思う。
私が自然生クラブの存在を知ったのは確か一昨年、2008年の秋頃で、その活動に興味を覚えてたびたびその所在地に足を運ぶようになった。今年の秋になって、自然生クラブが桜川市のホールで開かれる福祉関係の映画上映会で田楽舞を披露するという話を知り、自宅から桜川市までは遠かったけれど、折角なのでその会場を訪ねてみた。
前置きが長くなったが、これから書くのはそのイベントのことだ。
ハートフル映画祭inシトラス
これがイベントの正式名称で、上映された映画が『どんぐりの家』。
どういう映画なのかは、チラシに紹介文があるので、それを読んでもらうのがいいだろう。
>>>>
アニメ映画「どんぐりの家」は、実在するろう重複障害者の共同作業所をモデルにしたヒューマンドラマです。
ハンディを背負った子どもたちの成長を願い、苦しみながらも歩んでいく家族、それを支える人々の姿は、福祉の原点を問いかけるものです。
“桜川で「どんぐりの家」を観る会”では、この映画を通して、障害者への理解を深め、思いやりと優しさのあるまちづくりの輪を広げていきたいと考えています。
また当日は、この映画をいろいろな国で上映したいという留学生の思いに賛同し、募金活動を行います。
多くの国で「どんぐりの家」が上映されることを期待しています。
>>>>
そもそも私は映画のほうにさほど関心はなく、予備知識をまったく仕入れてなかった。会場に着いたのが上映開始ギリギリの時間で、映画が始まってようやく「えっ!? これってアニメだったの?」と気がつく始末。だけど上映が終わった後で、「この映画を観ることが出来て、本当に良かった」と思った。そして、「この映画をぜひとも、1人でも多くの人に観てもらいたい」とも思った。この映画にはそれだけの力がある。アニメだけれど(ただし一部に実写の場面もある)、アニメだから表現できたし、アニメだからここまで踏み込めて描くことが出来たし、アニメだからこそこれだけの訴える力を持てたのだと思う。
上映後には一般参加者を交えたフォーラムの時間が用意されており、そこで色々な方が感想を述べられたが、皆に共通していたのは「この映画からは多くのことを学ぶことが出来る」という意見だった。私もまったくその通りで、この映画から多くのことを学ばされたし、これからも多くの発見をしていくことだと思う。
その全てを書き出すのは難しいけれど、少しだけ例を挙げてみよう。
何よりも私が心を揺り動かされたのは、この映画が“障害者と共に生きる”ということをきれい事で終わらせず、きれい事だけではやっていけない現実を真正面から見据え、その有様をしっかりと描いていることだ。
映画の主人公は障害児を持つ母親。仮死状態で生まれた娘が、やがて重度の障害児であることが分かる。家庭に障害児を抱え込むという過酷な現実に打ちのめされ、幸せだった家庭が絶望に飲み込まれ荒廃していく有様が、映画では容赦なく描かれていく。子どもの介護に疲れて絶望する母親、家庭で安らぐことが出来ず妻にあたり散らし酒に溺れる父親、そんな親の目の前で動物のように本能のまま暴れる子ども、観ているこちらが「ここまで描いていいのか? この家族はどうなってしまうのだろう?」とハラハラしてしまうほどだが、結局その家族は一つの事件をきっかけとして、立ち直りの道を歩んでいくことになるのだ。観ている方もハラハラドギドキから、頑張れ頑張れとエールを送りたい気持ちになり、その後はただただ映画に引き込まれて最後まで観てしまった。
あと一つ。映画で描かれている、きれい事だけではやっていけない現実の例を。
小学校から高校までの十五年間、先生方の手厚い教育と訓練を受けて養護学校を卒業したものの、それを受け入れる場が社会にあまりにも少なく、結局、家に閉じこもってしまう障害児のケースだ。ただ家族に食べさせてもらうだけの生活で、学校で育まれた適応力も失われていき、健康状態も悪化する。親は年老いていき、親に先立たれたら生きていく術はない。
もしも自分が死んだら、この子はどうなってしまうのだろう?
そういう悩みを持つ、障害児を抱える親たちが集まって立ち上がった。
社会に受け入れる場がないのなら、自分たちでその場所を作ろうと。
それが障害児のための共同作業所、重度の障害児がハンディを気にすることなく働ける場所、それは『どんぐりの家』と名づけられた。
この“障害者を受け入れる場所を、当事者たちが社会の中に作る”ということが、映画の後半の重要なテーマになるのだけれど、私は映画を観ながら、今社会で問題になっている引きこもりやニートのことを連想してしまった。社会に生き甲斐を見出せず自宅に引きこもり、ただ親に面倒を見てもらう若者達のことが社会問題化した最初は、確か1980年代のことだったと思う。その若者も今や40代・50代の高年齢に達し、面倒を見る親が亡くなったら生活能力のないまま社会に放り出されてしまうということが、支援者の間で懸念されているというニュースをどこかで読んだ記憶がある。実際、ニートがホームレスになるケースも出始めているという。
かつての高度経済成長も、バブルの熱狂もどこへやら、今の日本の社会はすっかり元気をなくしているし、政治も経済もガタガタだ。引きこもりやニートの問題も日本社会の生きづらさの表れだとも思う。しかし生きづらい社会のしわ寄せを最も受けるのは、やはり大きなハンディを抱えた障害者とその家族だろう。しかし社会の中で最も困難を抱え、最も苦しんでいるはずの当事者達が立ち上がり、自分たちの手で『どんぐりの家』という行き場を作り出したのだ。これには当事者のみならず、大勢の人々の支援があってこそ出来たことなのだけれど、その運動の中心にあったのは常に当事者たちだった。
この映画はその運動の貴重な記録だし、それは障害者のみならず、共にこの社会で困難を抱えながら生きている大勢の人々にとって励みになり、また多くの学ぶべきことを与えてくれるだろう。
だから私は、出来るだけこの映画を1人でも多くの人に観てもらいたいと思う。
会場にはこの映画を観て感動し、これをモンゴルで上映するために頑張っている、3人の留学生の方もみえていた。既にモンゴル語の字幕付きのものをモンゴルで上映し、これからも上映を続けていくそうだが、映画を観た人はとてもテンションが上がっていたとか。日本から遠く離れたモンゴルでも感動の輪が広がっているようだ。
http://ayayukimeia.tsukuba.ch/e104142.html
自然生クラブ、これは筑波山の麓にある、知的障害児と共に暮らす共同体だ。
一般的には障害児のための"施設"という呼ばれ方をするのだろうけれど、責任者の柳瀬氏はあえて"共同体"という言葉を使っておられるようだ。実際、自然生クラブの運営方針はユニークで、単に障害児の世話をするのみならず、障害児と共に有機農業を営み、また障害児と共に田楽舞という舞踏を嗜み、国内そして国外でもたびたび公演を行っている。また自然生クラブの職員を中心に結成された百景社という劇団があり、クラブの所有する劇場もある。この劇場はもともとは米を貯蔵する蔵だったものを改造したもので、百景社の公演に使われる以外にも、地元のアーティストの公演に貸し出されたり、また福祉や有機農業の分野で活躍する専門家がここに招かれ、セミナーが開かれたりすることもある。
その活動範囲は単なる施設の枠を越え、さまざまな人々のつながる共同体として機能している。だから私も"施設"よりも"共同体"という呼び名の方が相応しいと思う。
私が自然生クラブの存在を知ったのは確か一昨年、2008年の秋頃で、その活動に興味を覚えてたびたびその所在地に足を運ぶようになった。今年の秋になって、自然生クラブが桜川市のホールで開かれる福祉関係の映画上映会で田楽舞を披露するという話を知り、自宅から桜川市までは遠かったけれど、折角なのでその会場を訪ねてみた。
前置きが長くなったが、これから書くのはそのイベントのことだ。
ハートフル映画祭inシトラス
これがイベントの正式名称で、上映された映画が『どんぐりの家』。
どういう映画なのかは、チラシに紹介文があるので、それを読んでもらうのがいいだろう。
>>>>
アニメ映画「どんぐりの家」は、実在するろう重複障害者の共同作業所をモデルにしたヒューマンドラマです。
ハンディを背負った子どもたちの成長を願い、苦しみながらも歩んでいく家族、それを支える人々の姿は、福祉の原点を問いかけるものです。
“桜川で「どんぐりの家」を観る会”では、この映画を通して、障害者への理解を深め、思いやりと優しさのあるまちづくりの輪を広げていきたいと考えています。
また当日は、この映画をいろいろな国で上映したいという留学生の思いに賛同し、募金活動を行います。
多くの国で「どんぐりの家」が上映されることを期待しています。
>>>>
そもそも私は映画のほうにさほど関心はなく、予備知識をまったく仕入れてなかった。会場に着いたのが上映開始ギリギリの時間で、映画が始まってようやく「えっ!? これってアニメだったの?」と気がつく始末。だけど上映が終わった後で、「この映画を観ることが出来て、本当に良かった」と思った。そして、「この映画をぜひとも、1人でも多くの人に観てもらいたい」とも思った。この映画にはそれだけの力がある。アニメだけれど(ただし一部に実写の場面もある)、アニメだから表現できたし、アニメだからここまで踏み込めて描くことが出来たし、アニメだからこそこれだけの訴える力を持てたのだと思う。
上映後には一般参加者を交えたフォーラムの時間が用意されており、そこで色々な方が感想を述べられたが、皆に共通していたのは「この映画からは多くのことを学ぶことが出来る」という意見だった。私もまったくその通りで、この映画から多くのことを学ばされたし、これからも多くの発見をしていくことだと思う。
その全てを書き出すのは難しいけれど、少しだけ例を挙げてみよう。
何よりも私が心を揺り動かされたのは、この映画が“障害者と共に生きる”ということをきれい事で終わらせず、きれい事だけではやっていけない現実を真正面から見据え、その有様をしっかりと描いていることだ。
映画の主人公は障害児を持つ母親。仮死状態で生まれた娘が、やがて重度の障害児であることが分かる。家庭に障害児を抱え込むという過酷な現実に打ちのめされ、幸せだった家庭が絶望に飲み込まれ荒廃していく有様が、映画では容赦なく描かれていく。子どもの介護に疲れて絶望する母親、家庭で安らぐことが出来ず妻にあたり散らし酒に溺れる父親、そんな親の目の前で動物のように本能のまま暴れる子ども、観ているこちらが「ここまで描いていいのか? この家族はどうなってしまうのだろう?」とハラハラしてしまうほどだが、結局その家族は一つの事件をきっかけとして、立ち直りの道を歩んでいくことになるのだ。観ている方もハラハラドギドキから、頑張れ頑張れとエールを送りたい気持ちになり、その後はただただ映画に引き込まれて最後まで観てしまった。
あと一つ。映画で描かれている、きれい事だけではやっていけない現実の例を。
小学校から高校までの十五年間、先生方の手厚い教育と訓練を受けて養護学校を卒業したものの、それを受け入れる場が社会にあまりにも少なく、結局、家に閉じこもってしまう障害児のケースだ。ただ家族に食べさせてもらうだけの生活で、学校で育まれた適応力も失われていき、健康状態も悪化する。親は年老いていき、親に先立たれたら生きていく術はない。
もしも自分が死んだら、この子はどうなってしまうのだろう?
そういう悩みを持つ、障害児を抱える親たちが集まって立ち上がった。
社会に受け入れる場がないのなら、自分たちでその場所を作ろうと。
それが障害児のための共同作業所、重度の障害児がハンディを気にすることなく働ける場所、それは『どんぐりの家』と名づけられた。
この“障害者を受け入れる場所を、当事者たちが社会の中に作る”ということが、映画の後半の重要なテーマになるのだけれど、私は映画を観ながら、今社会で問題になっている引きこもりやニートのことを連想してしまった。社会に生き甲斐を見出せず自宅に引きこもり、ただ親に面倒を見てもらう若者達のことが社会問題化した最初は、確か1980年代のことだったと思う。その若者も今や40代・50代の高年齢に達し、面倒を見る親が亡くなったら生活能力のないまま社会に放り出されてしまうということが、支援者の間で懸念されているというニュースをどこかで読んだ記憶がある。実際、ニートがホームレスになるケースも出始めているという。
かつての高度経済成長も、バブルの熱狂もどこへやら、今の日本の社会はすっかり元気をなくしているし、政治も経済もガタガタだ。引きこもりやニートの問題も日本社会の生きづらさの表れだとも思う。しかし生きづらい社会のしわ寄せを最も受けるのは、やはり大きなハンディを抱えた障害者とその家族だろう。しかし社会の中で最も困難を抱え、最も苦しんでいるはずの当事者達が立ち上がり、自分たちの手で『どんぐりの家』という行き場を作り出したのだ。これには当事者のみならず、大勢の人々の支援があってこそ出来たことなのだけれど、その運動の中心にあったのは常に当事者たちだった。
この映画はその運動の貴重な記録だし、それは障害者のみならず、共にこの社会で困難を抱えながら生きている大勢の人々にとって励みになり、また多くの学ぶべきことを与えてくれるだろう。
だから私は、出来るだけこの映画を1人でも多くの人に観てもらいたいと思う。
会場にはこの映画を観て感動し、これをモンゴルで上映するために頑張っている、3人の留学生の方もみえていた。既にモンゴル語の字幕付きのものをモンゴルで上映し、これからも上映を続けていくそうだが、映画を観た人はとてもテンションが上がっていたとか。日本から遠く離れたモンゴルでも感動の輪が広がっているようだ。
Posted by 岩崎綾之 at
20:43
│Comments(0)
2011年01月01日
2011年01月01日
暗い正月
わっはっはっは!! 年が明けたぞ!! 朝だ、太陽の光だ、気がついたら空が明るいぞ、もう憎たらしいくらいに。今年はでかいのがやって来るかもだぞ。景気の二番底とか、第二のリーマンショックか、原発のメルトダウンとか、日中軍事衝突の勃発とか、おっと日本の国債大暴落と日本円の紙屑化も忘れるな。さあ叫べ! 叫べ! Cry! Cry! Cry! Cry! Cry! Cr~~~~~y!
‥‥ふぅ、すっきりしたぜ。あの気が滅入る超イタイ作、いやCGてんこ盛りの超大作『2012』を映画館で見たのは一昨年の話だったか? オカルト情報によれば地球規模の大異変が起こるらしいあの年の到来まで余すところあと1年を切った。これじゃ新年到来のカウントダウンがまるで破滅へのカウントダウンに思えてくるじゃないか。だからオレは今回の年末年始、賑やかな場所には行かず、新年を迎えるカウントダウンのイベントなんかそっちのけで、不景気の真っ只中にある地元の地方都市でひっそりと過ごした。いや折角、東京まで行って金稼いでいるんだから、少しは地元に金を落さないとな。
しっかし客がたった4人しか入っていないファミレスとか、新年到来の瞬間もひっそりと静まっている駅前とか、そんな場所で迎える新年もクールだ。いや心が寒くなるって? 近くのお寺からは除夜の鐘のぼわぁ~~んという音が響いてきて、暗く静まった景色の中で聞くと、心の中まであの鐘の音が染み込んでくるっつーか、諸行無常って言葉がしっくりくるんだよな。鐘を聞いているうちにこの世とあの世が重なっちゃったみたいな感じがしてくるしさ。
さて、そろそろ出かけるか。カラオケで歌った後は、筑波山で初詣だ。その後はネカフェにこもるぞ。
‥‥‥‥‥‥‥‥と、ここまで書いたのが今日の昼前。で、今は夜中の10時半近く。はい、カラオケで歌ってきました。筑波山の神社にも行ってきました。今はネットカフェにこもって、USBメモリーに記憶しといた文章をブログに貼り付けました。自宅はまだネットが使えないので、どうしてもUPまでのタイムラグが長くなっちゃうんですよ~だ。
‥‥ふぅ、すっきりしたぜ。あの気が滅入る超イタイ作、いやCGてんこ盛りの超大作『2012』を映画館で見たのは一昨年の話だったか? オカルト情報によれば地球規模の大異変が起こるらしいあの年の到来まで余すところあと1年を切った。これじゃ新年到来のカウントダウンがまるで破滅へのカウントダウンに思えてくるじゃないか。だからオレは今回の年末年始、賑やかな場所には行かず、新年を迎えるカウントダウンのイベントなんかそっちのけで、不景気の真っ只中にある地元の地方都市でひっそりと過ごした。いや折角、東京まで行って金稼いでいるんだから、少しは地元に金を落さないとな。
しっかし客がたった4人しか入っていないファミレスとか、新年到来の瞬間もひっそりと静まっている駅前とか、そんな場所で迎える新年もクールだ。いや心が寒くなるって? 近くのお寺からは除夜の鐘のぼわぁ~~んという音が響いてきて、暗く静まった景色の中で聞くと、心の中まであの鐘の音が染み込んでくるっつーか、諸行無常って言葉がしっくりくるんだよな。鐘を聞いているうちにこの世とあの世が重なっちゃったみたいな感じがしてくるしさ。
さて、そろそろ出かけるか。カラオケで歌った後は、筑波山で初詣だ。その後はネカフェにこもるぞ。
‥‥‥‥‥‥‥‥と、ここまで書いたのが今日の昼前。で、今は夜中の10時半近く。はい、カラオケで歌ってきました。筑波山の神社にも行ってきました。今はネットカフェにこもって、USBメモリーに記憶しといた文章をブログに貼り付けました。自宅はまだネットが使えないので、どうしてもUPまでのタイムラグが長くなっちゃうんですよ~だ。
2011年01月01日
黒い正月
また新しい年がやって来ました。
今年もよろしく。
この1年、関東で大地震が起きませんよーに。
東海地震が起きませんよーに。
原発がメルトダウンしませんよーに。
国債が大暴落して円が紙くずになりませんよーに。
北朝鮮のミサイルが飛んできませんよーに。
あと1年間無事に生き延びて、来年の正月を迎えられますよーに。
‥‥なんてね。
今年もよろしく。
この1年、関東で大地震が起きませんよーに。
東海地震が起きませんよーに。
原発がメルトダウンしませんよーに。
国債が大暴落して円が紙くずになりませんよーに。
北朝鮮のミサイルが飛んできませんよーに。
あと1年間無事に生き延びて、来年の正月を迎えられますよーに。
‥‥なんてね。

2010年11月25日
どんぐりの家
自然生クラブ、これは筑波山の麓にある、知的障害児と共に暮らす共同体だ。
一般的には障害児のための"施設"という呼ばれ方をするのだろうけれど、責任者の柳瀬氏はあえて"共同体"という言葉を使っておられるようだ。実際、自然生クラブの運営方針はユニークで、単に障害児の世話をするのみならず、障害児と共に有機農業を営み、また障害児と共に田楽舞という舞踏を嗜み、国内そして国外でもたびたび公演を行っている。また自然生クラブの職員を中心に結成された百景社という劇団があり、クラブの所有する劇場もある。この劇場はもともとは米を貯蔵する蔵だったものを改造したもので、百景社の公演に使われる以外にも、地元のアーティストの公演に貸し出されたり、また福祉や有機農業の分野で活躍する専門家がここに招かれ、セミナーが開かれたりすることもある。
その活動範囲は単なる施設の枠を越え、さまざまな人々のつながる共同体として機能している。だから私も"施設"よりも"共同体"という呼び名の方が相応しいと思う。
私が自然生クラブの存在を知ったのは確か一昨年、2008年の秋頃で、その活動に興味を覚えてたびたびその所在地に足を運ぶようになった。今年の秋になって、自然生クラブが桜川市のホールで開かれる福祉関係の映画上映会で田楽舞を披露するという話を知り、自宅から桜川市までは遠かったけれど、折角なのでその会場を訪ねてみた。
前置きが長くなったが、これから書くのはそのイベントのことだ。
ハートフル映画祭inシトラス
これがイベントの正式名称で、上映された映画が『どんぐりの家』。
どういう映画なのかは、チラシに紹介文があるので、それを読んでもらうのがいいだろう。
>>>>
アニメ映画「どんぐりの家」は、実在するろう重複障害者の共同作業所をモデルにしたヒューマンドラマです。
ハンディを背負った子どもたちの成長を願い、苦しみながらも歩んでいく家族、それを支える人々の姿は、福祉の原点を問いかけるものです。
“桜川で「どんぐりの家」を観る会”では、この映画を通して、障害者への理解を深め、思いやりと優しさのあるまちづくりの輪を広げていきたいと考えています。
また当日は、この映画をいろいろな国で上映したいという留学生の思いに賛同し、募金活動を行います。
多くの国で「どんぐりの家」が上映されることを期待しています。
>>>>
そもそも私は映画のほうにさほど関心はなく、予備知識をまったく仕入れてなかった。会場に着いたのが上映開始ギリギリの時間で、映画が始まってようやく「えっ!? これってアニメだったの?」と気がつく始末。だけど上映が終わった後で、「この映画を観ることが出来て、本当に良かった」と思った。そして、「この映画をぜひとも、1人でも多くの人に観てもらいたい」とも思った。この映画にはそれだけの力がある。アニメだけれど(ただし一部に実写の場面もある)、アニメだから表現できたし、アニメだからここまで踏み込めて描くことが出来たし、アニメだからこそこれだけの訴える力を持てたのだと思う。
上映後には一般参加者を交えたフォーラムの時間が用意されており、そこで色々な方が感想を述べられたが、皆に共通していたのは「この映画からは多くのことを学ぶことが出来る」という意見だった。私もまったくその通りで、この映画から多くのことを学ばされたし、これからも多くの発見をしていくことだと思う。
その全てを書き出すのは難しいけれど、少しだけ例を挙げてみよう。
何よりも私が心を揺り動かされたのは、この映画が“障害者と共に生きる”ということをきれい事で終わらせず、きれい事だけではやっていけない現実を真正面から見据え、その有様をしっかりと描いていることだ。
映画の主人公は障害児を持つ母親。仮死状態で生まれた娘が、やがて重度の障害児であることが分かる。家庭に障害児を抱え込むという過酷な現実に打ちのめされ、幸せだった家庭が絶望に飲み込まれ荒廃していく有様が、映画では容赦なく描かれていく。子どもの介護に疲れて絶望する母親、家庭で安らぐことが出来ず妻にあたり散らし酒に溺れる父親、そんな親の目の前で動物のように本能のまま暴れる子ども、観ているこちらが「ここまで描いていいのか? この家族はどうなってしまうのだろう?」とハラハラしてしまうほどだが、結局その家族は一つの事件をきっかけとして、立ち直りの道を歩んでいくことになるのだ。観ている方もハラハラドギドキから、頑張れ頑張れとエールを送りたい気持ちになり、その後はただただ映画に引き込まれて最後まで観てしまった。
あと一つ。映画で描かれている、きれい事だけではやっていけない現実の例を。
小学校から高校までの十五年間、先生方の手厚い教育と訓練を受けて養護学校を卒業したものの、それを受け入れる場が社会にあまりにも少なく、結局、家に閉じこもってしまう障害児のケースだ。ただ家族に食べさせてもらうだけの生活で、学校で育まれた適応力も失われていき、健康状態も悪化する。親は年老いていき、親に先立たれたら生きていく術はない。
もしも自分が死んだら、この子はどうなってしまうのだろう?
そういう悩みを持つ、障害児を抱える親たちが集まって立ち上がった。
社会に受け入れる場がないのなら、自分たちでその場所を作ろうと。
それが障害児のための共同作業所、重度の障害児がハンディを気にすることなく働ける場所、それは『どんぐりの家』と名づけられた。
この“障害者を受け入れる場所を、当事者たちが社会の中に作る”ということが、映画の後半の重要なテーマになるのだけれど、私は映画を観ながら、今社会で問題になっている引きこもりやニートのことを連想してしまった。社会に生き甲斐を見出せず自宅に引きこもり、ただ親に面倒を見てもらう若者達のことが社会問題化した最初は、確か1980年代のことだったと思う。その若者も今や40代・50代の高年齢に達し、面倒を見る親が亡くなったら生活能力のないまま社会に放り出されてしまうということが、支援者の間で懸念されているというニュースをどこかで読んだ記憶がある。実際、ニートがホームレスになるケースも出始めているという。
かつての高度経済成長も、バブルの熱狂もどこへやら、今の日本の社会はすっかり元気をなくしているし、政治も経済もガタガタだ。引きこもりやニートの問題も日本社会の生きづらさの表れだとも思う。しかし生きづらい社会のしわ寄せを最も受けるのは、やはり大きなハンディを抱えた障害者とその家族だろう。しかし社会の中で最も困難を抱え、最も苦しんでいるはずの当事者達が立ち上がり、自分たちの手で『どんぐりの家』という行き場を作り出したのだ。これには当事者のみならず、大勢の人々の支援があってこそ出来たことなのだけれど、その運動の中心にあったのは常に当事者たちだった。
この映画はその運動の貴重な記録だし、それは障害者のみならず、共にこの社会で困難を抱えながら生きている大勢の人々にとって励みになり、また多くの学ぶべきことを与えてくれるだろう。
だから私は、出来るだけこの映画を1人でも多くの人に観てもらいたいと思う。
会場にはこの映画を観て感動し、これをモンゴルで上映するために頑張っている、3人の留学生の方もみえていた。既にモンゴル語の字幕付きのものをモンゴルで上映し、これからも上映を続けていくそうだが、映画を観た人はとてもテンションが上がっていたとか。日本から遠く離れたモンゴルでも感動の輪が広がっているようだ。
一般的には障害児のための"施設"という呼ばれ方をするのだろうけれど、責任者の柳瀬氏はあえて"共同体"という言葉を使っておられるようだ。実際、自然生クラブの運営方針はユニークで、単に障害児の世話をするのみならず、障害児と共に有機農業を営み、また障害児と共に田楽舞という舞踏を嗜み、国内そして国外でもたびたび公演を行っている。また自然生クラブの職員を中心に結成された百景社という劇団があり、クラブの所有する劇場もある。この劇場はもともとは米を貯蔵する蔵だったものを改造したもので、百景社の公演に使われる以外にも、地元のアーティストの公演に貸し出されたり、また福祉や有機農業の分野で活躍する専門家がここに招かれ、セミナーが開かれたりすることもある。
その活動範囲は単なる施設の枠を越え、さまざまな人々のつながる共同体として機能している。だから私も"施設"よりも"共同体"という呼び名の方が相応しいと思う。
私が自然生クラブの存在を知ったのは確か一昨年、2008年の秋頃で、その活動に興味を覚えてたびたびその所在地に足を運ぶようになった。今年の秋になって、自然生クラブが桜川市のホールで開かれる福祉関係の映画上映会で田楽舞を披露するという話を知り、自宅から桜川市までは遠かったけれど、折角なのでその会場を訪ねてみた。
前置きが長くなったが、これから書くのはそのイベントのことだ。
ハートフル映画祭inシトラス
これがイベントの正式名称で、上映された映画が『どんぐりの家』。
どういう映画なのかは、チラシに紹介文があるので、それを読んでもらうのがいいだろう。
>>>>
アニメ映画「どんぐりの家」は、実在するろう重複障害者の共同作業所をモデルにしたヒューマンドラマです。
ハンディを背負った子どもたちの成長を願い、苦しみながらも歩んでいく家族、それを支える人々の姿は、福祉の原点を問いかけるものです。
“桜川で「どんぐりの家」を観る会”では、この映画を通して、障害者への理解を深め、思いやりと優しさのあるまちづくりの輪を広げていきたいと考えています。
また当日は、この映画をいろいろな国で上映したいという留学生の思いに賛同し、募金活動を行います。
多くの国で「どんぐりの家」が上映されることを期待しています。
>>>>
そもそも私は映画のほうにさほど関心はなく、予備知識をまったく仕入れてなかった。会場に着いたのが上映開始ギリギリの時間で、映画が始まってようやく「えっ!? これってアニメだったの?」と気がつく始末。だけど上映が終わった後で、「この映画を観ることが出来て、本当に良かった」と思った。そして、「この映画をぜひとも、1人でも多くの人に観てもらいたい」とも思った。この映画にはそれだけの力がある。アニメだけれど(ただし一部に実写の場面もある)、アニメだから表現できたし、アニメだからここまで踏み込めて描くことが出来たし、アニメだからこそこれだけの訴える力を持てたのだと思う。
上映後には一般参加者を交えたフォーラムの時間が用意されており、そこで色々な方が感想を述べられたが、皆に共通していたのは「この映画からは多くのことを学ぶことが出来る」という意見だった。私もまったくその通りで、この映画から多くのことを学ばされたし、これからも多くの発見をしていくことだと思う。
その全てを書き出すのは難しいけれど、少しだけ例を挙げてみよう。
何よりも私が心を揺り動かされたのは、この映画が“障害者と共に生きる”ということをきれい事で終わらせず、きれい事だけではやっていけない現実を真正面から見据え、その有様をしっかりと描いていることだ。
映画の主人公は障害児を持つ母親。仮死状態で生まれた娘が、やがて重度の障害児であることが分かる。家庭に障害児を抱え込むという過酷な現実に打ちのめされ、幸せだった家庭が絶望に飲み込まれ荒廃していく有様が、映画では容赦なく描かれていく。子どもの介護に疲れて絶望する母親、家庭で安らぐことが出来ず妻にあたり散らし酒に溺れる父親、そんな親の目の前で動物のように本能のまま暴れる子ども、観ているこちらが「ここまで描いていいのか? この家族はどうなってしまうのだろう?」とハラハラしてしまうほどだが、結局その家族は一つの事件をきっかけとして、立ち直りの道を歩んでいくことになるのだ。観ている方もハラハラドギドキから、頑張れ頑張れとエールを送りたい気持ちになり、その後はただただ映画に引き込まれて最後まで観てしまった。
あと一つ。映画で描かれている、きれい事だけではやっていけない現実の例を。
小学校から高校までの十五年間、先生方の手厚い教育と訓練を受けて養護学校を卒業したものの、それを受け入れる場が社会にあまりにも少なく、結局、家に閉じこもってしまう障害児のケースだ。ただ家族に食べさせてもらうだけの生活で、学校で育まれた適応力も失われていき、健康状態も悪化する。親は年老いていき、親に先立たれたら生きていく術はない。
もしも自分が死んだら、この子はどうなってしまうのだろう?
そういう悩みを持つ、障害児を抱える親たちが集まって立ち上がった。
社会に受け入れる場がないのなら、自分たちでその場所を作ろうと。
それが障害児のための共同作業所、重度の障害児がハンディを気にすることなく働ける場所、それは『どんぐりの家』と名づけられた。
この“障害者を受け入れる場所を、当事者たちが社会の中に作る”ということが、映画の後半の重要なテーマになるのだけれど、私は映画を観ながら、今社会で問題になっている引きこもりやニートのことを連想してしまった。社会に生き甲斐を見出せず自宅に引きこもり、ただ親に面倒を見てもらう若者達のことが社会問題化した最初は、確か1980年代のことだったと思う。その若者も今や40代・50代の高年齢に達し、面倒を見る親が亡くなったら生活能力のないまま社会に放り出されてしまうということが、支援者の間で懸念されているというニュースをどこかで読んだ記憶がある。実際、ニートがホームレスになるケースも出始めているという。
かつての高度経済成長も、バブルの熱狂もどこへやら、今の日本の社会はすっかり元気をなくしているし、政治も経済もガタガタだ。引きこもりやニートの問題も日本社会の生きづらさの表れだとも思う。しかし生きづらい社会のしわ寄せを最も受けるのは、やはり大きなハンディを抱えた障害者とその家族だろう。しかし社会の中で最も困難を抱え、最も苦しんでいるはずの当事者達が立ち上がり、自分たちの手で『どんぐりの家』という行き場を作り出したのだ。これには当事者のみならず、大勢の人々の支援があってこそ出来たことなのだけれど、その運動の中心にあったのは常に当事者たちだった。
この映画はその運動の貴重な記録だし、それは障害者のみならず、共にこの社会で困難を抱えながら生きている大勢の人々にとって励みになり、また多くの学ぶべきことを与えてくれるだろう。
だから私は、出来るだけこの映画を1人でも多くの人に観てもらいたいと思う。
会場にはこの映画を観て感動し、これをモンゴルで上映するために頑張っている、3人の留学生の方もみえていた。既にモンゴル語の字幕付きのものをモンゴルで上映し、これからも上映を続けていくそうだが、映画を観た人はとてもテンションが上がっていたとか。日本から遠く離れたモンゴルでも感動の輪が広がっているようだ。
2010年11月25日
桜川市へ行ってきました
自然生クラブ──これを“しぜんなまくらぶ”と読んではいけません。いつぞや、そんな風に読んでる人を見かけたもんで。正しくは“じねんじょくらぶ”と読みます。
ま、生の自然と向き合って生活してるとこだし、僕は“しぜんなま”でもいいんじゃないかと思ったりしてるけど。
これは筑波山の麓あたりに所在するNPO法人、知的障害児と共に生きる共同体です。と書くと難しそうで近寄り難い感じがするけど、僕の印象では障害児と家族のように暮らしながら、農作業やったり歌ったり踊ったり芝居をやったりしている元気な皆さんです。
ここが劇団・百景社のスポンサーをやっていることもあって僕は興味を覚え、筑波山の麓で開かれるここのイベントに足を運ぶようになり、今年の5月には田植えにも参加しました。もっとも僕は現地へやって来たものの、泥んこ虫だらけの田んぼに恐れをなして立ちすくんでしまい(有機農業で農薬使わないから虫が湧くんだよ~。カエルもいて、参加した子どもが喜んで捕まえてたぞ~)、ずっと田んぼの畦で見学してました。情けねぇ~。
で、この秋になってこの自然生クラブが桜川市で田楽舞を披露するというので、久しぶりに自然生の皆さんの顔を見たいと思って、桜川市まで行ってきました。
自宅から桜川市まではちょっと遠かったけど。
いや、ちょっとなんてもんじゃないな。
片道、40キロ以上。自転車で行くには‥‥水戸よりは近いけどさ。
でも途中、石岡とか羽鳥とかいう地名が看板に書いてあったりするし。
そのまま走っていったら水戸まで行っちまいそうだ。
だって会場のホールが桜川市の北のほうだし。せめて真壁の辺りだったらまだ行きやすかったんだけど。
そうそう、真壁の町は途中で通過した。筑波石の産出地だけあって、町のいたる所に石屋さんがあって石像がずらずら立ち並んでいる。観音様とか七福神とかお稲荷さんとかゴジラとかポケモンっぽいのとか韓国のトルハルバンっぽいのとか何だかよくわからないキャラとか。なんだか町全体が異次元ムードか異世界ムードに包まれてるみたいで、折角だから写真を撮っておこうかとも思ったけど、行きは時間がなさそうだったんで余計なことに時間つぶすのは辞めた。で、帰りは日が落ちて暗くなってしかも腹減ってふらふらして写真撮るどころじゃない。あ、フラッシュ使えば良かったのか。写真撮るのはまた今度にしよう。
そういえば行きと帰りに立ち寄ったコンビニにも、なぜか招き猫の石像が。
やはり筑波山の麓にあるコンビニは、普通と違う。
‥‥何の話だ? そうだ自然生だ。
この話はおちゃらけた文体で書くのもなんだし、ブログに別の項目立てて書いたんでよろしく。『どんぐりの家』がそうだ。読んでくれ。
ま、生の自然と向き合って生活してるとこだし、僕は“しぜんなま”でもいいんじゃないかと思ったりしてるけど。
これは筑波山の麓あたりに所在するNPO法人、知的障害児と共に生きる共同体です。と書くと難しそうで近寄り難い感じがするけど、僕の印象では障害児と家族のように暮らしながら、農作業やったり歌ったり踊ったり芝居をやったりしている元気な皆さんです。
ここが劇団・百景社のスポンサーをやっていることもあって僕は興味を覚え、筑波山の麓で開かれるここのイベントに足を運ぶようになり、今年の5月には田植えにも参加しました。もっとも僕は現地へやって来たものの、泥んこ虫だらけの田んぼに恐れをなして立ちすくんでしまい(有機農業で農薬使わないから虫が湧くんだよ~。カエルもいて、参加した子どもが喜んで捕まえてたぞ~)、ずっと田んぼの畦で見学してました。情けねぇ~。
で、この秋になってこの自然生クラブが桜川市で田楽舞を披露するというので、久しぶりに自然生の皆さんの顔を見たいと思って、桜川市まで行ってきました。
自宅から桜川市まではちょっと遠かったけど。
いや、ちょっとなんてもんじゃないな。
片道、40キロ以上。自転車で行くには‥‥水戸よりは近いけどさ。
でも途中、石岡とか羽鳥とかいう地名が看板に書いてあったりするし。
そのまま走っていったら水戸まで行っちまいそうだ。
だって会場のホールが桜川市の北のほうだし。せめて真壁の辺りだったらまだ行きやすかったんだけど。
そうそう、真壁の町は途中で通過した。筑波石の産出地だけあって、町のいたる所に石屋さんがあって石像がずらずら立ち並んでいる。観音様とか七福神とかお稲荷さんとかゴジラとかポケモンっぽいのとか韓国のトルハルバンっぽいのとか何だかよくわからないキャラとか。なんだか町全体が異次元ムードか異世界ムードに包まれてるみたいで、折角だから写真を撮っておこうかとも思ったけど、行きは時間がなさそうだったんで余計なことに時間つぶすのは辞めた。で、帰りは日が落ちて暗くなってしかも腹減ってふらふらして写真撮るどころじゃない。あ、フラッシュ使えば良かったのか。写真撮るのはまた今度にしよう。
そういえば行きと帰りに立ち寄ったコンビニにも、なぜか招き猫の石像が。
やはり筑波山の麓にあるコンビニは、普通と違う。
‥‥何の話だ? そうだ自然生だ。
この話はおちゃらけた文体で書くのもなんだし、ブログに別の項目立てて書いたんでよろしく。『どんぐりの家』がそうだ。読んでくれ。
2010年11月12日
『ドン・キホーテ』の公演を振り返って
かなり時間が過ぎてしまったけれど、『ドン・キホーテ』の公演のことを書いておこう。公演の楽日から10日とちょっとしか過ぎてないけど、個人的には「あっという間に終わってしまった」という気分だ。長々と思い出にひたることもなく、打ち上げの翌日は半日寝込んで、夜になったらまた以前と同じように深夜のお仕事に出勤。いつもと同じような繰り返しの毎日が始まってしまうと、水戸芸術館の舞台に立った高揚感もゴチャゴチャした日常の中に紛れ込んで、あまり思い出すことも無くなってしまった。
でも時間のある時には、少しずつ思い出しながら書いておこう。
今の私の心境としては、これで一つまた一つの通過点を通り過ぎたという気持ちだ。
これは水戸演劇学校の講師、長谷川さんが言っていたことだけれど、芝居を続けるということは長い旅の中で一里塚を一つまた一つと越えていくことに似ている。あるいは岩登りで、岩肌に楔(くさび)を一つまた一つと打ち込んでいくことに似ているという。私もその通りだと思う。
水戸に通い続ける間、舞台が終わると寂しくなるという仲間の声をよく聞いたし、楽日の日は初日と中日の公演とはうってかわって寂寥感のようなものが漂っていた。が、私はその寂寥感を心地よくも感じていた。馴れてしまえばそれも悪くはない。
そもそも私は寂しいという感傷的な気分に浸るのは得意じゃないし、たとえそうなりそうな時があったとしても、できるだけ感傷的にならないように努める。寂しいなんて思う暇があるなら、次の一里塚、次の楔をどこにするか、それを探すことに集中しろと。いつもそんな考えでいる。
さて、次はどこを目指そうか? 次に越えるべき一里塚は? 次に楔を打ち込むべき場所は? さしあたって年末年始までは、演劇に関しては大きな山を越えることもなく、ゆったりしたペースで進むことになりそうだ。おっと、12月25日のクリスマスにはバリリー座と地元劇団の合同公演があったか。土浦の小さな会場を借りてやる公演だ。あと11月から12月にかけては土浦と水戸で、地元劇団の公演が色々と催されるので、しばらくは観劇であちこち飛び回ることになりそう。12月には劇団SCOTの公演が東京であので観に行きたいのだけれど、こっちは入場料が5千円と結構なお値段。お金、大丈夫かな?
そう言えば、『ドン・キホーテ』に関わってきた2ヶ月の間に、一つの変わった出来事があった。私の住んでいるアパートの隣には空き家があり、長いこと放置されていた。空き家の敷地内にはプラタナスの大きな木が生えていて、夏場には虫に食われたりしたけれど、風が吹くと葉と葉が擦れあってサワサワと音を立てる。2階のベランダから眺めると、そこにあるのは寂れた景色だったけれど、私はずっとその景色に馴染んでいた。
ところが公演も近づいた某日。突然に解体業者がやってきて、重機を使って空き家を取り壊してしまった。プラタナスの木も切られてしまい、公演の頃には更地になってしまった。今、ベランダから見えるのはほとんど草も生えていないのっぺりした更地と、その向こう側の人家、そしてさらに向こう側の森だ。見晴らしはよくなったが殺風景になってしまった景色。しかし、さほど遠くない場所に見える森は、午後になると柔らかな日差しが当たって、風光明媚とはいかないまでもそれなりに美しい。
部屋から見える景色が変わったことも、人生の一つの節目かも?
でも時間のある時には、少しずつ思い出しながら書いておこう。
今の私の心境としては、これで一つまた一つの通過点を通り過ぎたという気持ちだ。
これは水戸演劇学校の講師、長谷川さんが言っていたことだけれど、芝居を続けるということは長い旅の中で一里塚を一つまた一つと越えていくことに似ている。あるいは岩登りで、岩肌に楔(くさび)を一つまた一つと打ち込んでいくことに似ているという。私もその通りだと思う。
水戸に通い続ける間、舞台が終わると寂しくなるという仲間の声をよく聞いたし、楽日の日は初日と中日の公演とはうってかわって寂寥感のようなものが漂っていた。が、私はその寂寥感を心地よくも感じていた。馴れてしまえばそれも悪くはない。
そもそも私は寂しいという感傷的な気分に浸るのは得意じゃないし、たとえそうなりそうな時があったとしても、できるだけ感傷的にならないように努める。寂しいなんて思う暇があるなら、次の一里塚、次の楔をどこにするか、それを探すことに集中しろと。いつもそんな考えでいる。
さて、次はどこを目指そうか? 次に越えるべき一里塚は? 次に楔を打ち込むべき場所は? さしあたって年末年始までは、演劇に関しては大きな山を越えることもなく、ゆったりしたペースで進むことになりそうだ。おっと、12月25日のクリスマスにはバリリー座と地元劇団の合同公演があったか。土浦の小さな会場を借りてやる公演だ。あと11月から12月にかけては土浦と水戸で、地元劇団の公演が色々と催されるので、しばらくは観劇であちこち飛び回ることになりそう。12月には劇団SCOTの公演が東京であので観に行きたいのだけれど、こっちは入場料が5千円と結構なお値段。お金、大丈夫かな?
そう言えば、『ドン・キホーテ』に関わってきた2ヶ月の間に、一つの変わった出来事があった。私の住んでいるアパートの隣には空き家があり、長いこと放置されていた。空き家の敷地内にはプラタナスの大きな木が生えていて、夏場には虫に食われたりしたけれど、風が吹くと葉と葉が擦れあってサワサワと音を立てる。2階のベランダから眺めると、そこにあるのは寂れた景色だったけれど、私はずっとその景色に馴染んでいた。
ところが公演も近づいた某日。突然に解体業者がやってきて、重機を使って空き家を取り壊してしまった。プラタナスの木も切られてしまい、公演の頃には更地になってしまった。今、ベランダから見えるのはほとんど草も生えていないのっぺりした更地と、その向こう側の人家、そしてさらに向こう側の森だ。見晴らしはよくなったが殺風景になってしまった景色。しかし、さほど遠くない場所に見える森は、午後になると柔らかな日差しが当たって、風光明媚とはいかないまでもそれなりに美しい。
部屋から見える景色が変わったことも、人生の一つの節目かも?
2010年11月12日
もうすぐ年の暮れ
あれは一昨日、10月10日のことだ。
夜勤明け、会社の帰りに送迎バスの窓から外を見ると、朝焼けで立ち並ぶビルが紅に染まっていた。いつもはうつらうつらしているのに、この日は妙に目が冴えていて。いつも眠気のカーテン越しに見ていた景色がとても新鮮に見えた。
後ろの座席からは日本語じゃない会話が聞こえてくる。喋っているのは私と同じく仕事を終えたばかりの、年齢は30歳前後になる2人の女性だ。言葉の意味は分からないけど、楽しそうなその声を聞いて、私は在日外国人の労働者もいる仕事場で働いているということに、今さらながらに気付かされた。
私の働く職場は有明にある。私が年末によく訪れる場所だ。紅に染まった高層ビルの群れ、どこか浮世離れ景色をした景色を見ながら、そういえばもうじき年の暮れがやってくるのだなと考えていた。
ビルの合間からは富士山も見える。まだ秋のせいか、山頂を覆う雪はそんなに多くない。いつぞやの正月も、ビルの向こうに富士山を見たことがある。年月の移り変わりを感じさせる景色だ。
思えば今年は失業と金欠に振り回され続けた年だったけれど、来年は‥‥もっと酷い年だったりして。来年の今頃は「去年はよかったな~」なんて愚痴ってるかもしれないけれど、そんなのは嫌だぞ。
夜勤明け、会社の帰りに送迎バスの窓から外を見ると、朝焼けで立ち並ぶビルが紅に染まっていた。いつもはうつらうつらしているのに、この日は妙に目が冴えていて。いつも眠気のカーテン越しに見ていた景色がとても新鮮に見えた。
後ろの座席からは日本語じゃない会話が聞こえてくる。喋っているのは私と同じく仕事を終えたばかりの、年齢は30歳前後になる2人の女性だ。言葉の意味は分からないけど、楽しそうなその声を聞いて、私は在日外国人の労働者もいる仕事場で働いているということに、今さらながらに気付かされた。
私の働く職場は有明にある。私が年末によく訪れる場所だ。紅に染まった高層ビルの群れ、どこか浮世離れ景色をした景色を見ながら、そういえばもうじき年の暮れがやってくるのだなと考えていた。
ビルの合間からは富士山も見える。まだ秋のせいか、山頂を覆う雪はそんなに多くない。いつぞやの正月も、ビルの向こうに富士山を見たことがある。年月の移り変わりを感じさせる景色だ。
思えば今年は失業と金欠に振り回され続けた年だったけれど、来年は‥‥もっと酷い年だったりして。来年の今頃は「去年はよかったな~」なんて愚痴ってるかもしれないけれど、そんなのは嫌だぞ。
2010年10月25日
ヤバいネタ自粛中
お金がなくて家からネットに入れなくなったんで、家でノートパソに打ち込んだ文章をフラッシュメモリに記録して、ネットカフェに持っていってアップしてまふ。当分、こういうのが続きそうです。
お金がなくても演劇は続けてます。が、日記を読み返してみるとヤバいカキコばっかり。一緒に演劇やってる劇団員の一部にはバレバレになっちゃったみたいだけど、ついこの前も色々あって、こんなのが演出担当の某氏にバレるとなんだか非常にマズ~いことになりそうなので、当分の間、ヤバい系のカキコは自粛させていただきまふ。
その代わり、今、関わっている芝居の本公演が全部終わったら、打ち上げパーティーで全部バラしていいよってことにしてあるんで、お楽しみに。
うわ~ん、打ち上げが怖いよ~!!
お金がなくても演劇は続けてます。が、日記を読み返してみるとヤバいカキコばっかり。一緒に演劇やってる劇団員の一部にはバレバレになっちゃったみたいだけど、ついこの前も色々あって、こんなのが演出担当の某氏にバレるとなんだか非常にマズ~いことになりそうなので、当分の間、ヤバい系のカキコは自粛させていただきまふ。
その代わり、今、関わっている芝居の本公演が全部終わったら、打ち上げパーティーで全部バラしていいよってことにしてあるんで、お楽しみに。
うわ~ん、打ち上げが怖いよ~!!
2010年10月15日
10月10~11日の日記~相変わらず水戸に泊まりです
この日も水戸で稽古があって、次の日も稽古日。
この前の稽古の時は水戸駅近くのマックに泊まったけど、今、家計がヤバい。ちょっとでも金を節約しようと思い、水戸の電波塔の近くに手頃なサークル型のベンチを見つけたんで、試しにそこで寝てみることにした。
だけど今どきのベンチはホームレスの寝転がり防止のためか、座席にでっぱりが多くて座ることは出来ても寝転がりにくい構造になってる。これって挑戦かよ、受けてやろうじゃん。と気張って寝転がってみたら、でっぱりが背中に当たってやっぱり痛い。試しに下にレインコートとか敷いて寝てみたら、少しは寝やすくなったけど、背中に刺激が加わるもんだからなかなか眠れない。ベンチの横を車がびゅんびゅん通り過ぎていく。ここで運転ミスった車がベンチに突っ込んできたら、あの世行きかもな~なんて思っていたら、周りが湿っぽくなって霧が出てきた。上を見ると、夜空に霧の塊がふわ~っと流れている。 辺りの景色もだんだん霧に包まれて、マジであの世に行ったような気分になってくる。
寝づらいベンチなので大通りにあるベンチに移動。座席が平べったくて寝っ転がれるベンチへ移動。さあこれで眠れるかなと思っていたら、だんだん寒くなってくるし、すぐ横の通りを暴走族のバイクがでけぇ音出して通り過ぎるしで、眠れない。
こんな所で何やってんだオレ? 素直にマックで寝ようっと。
そういうわけで結局、今回も駅近くのマックに泊まった。
やべぇぞ、マジで所持金が限界だぞ。次もマックに泊まったら、次の稽古は飲まず食わずでやることになりそうだぞ。
どうすっかな~~~~~~~~~?
考えた末に気がついた。
そうだ、水戸には千波湖があるじゃないか。あそこは公園になってるし、夏場過ぎた今なら蚊も出なさそうだし。
マックを出てから自転車で千波湖の畔を物色してみると、あちこちに手頃なベンチが置いてある。張り出されている注意書きを読んでみると、公園は一部施設を除き24時間利用可能とか書いてある。
あ、そう。んじゃ今度の稽古日はここで寝よっと。
寒くなってきたけど、寝袋に包まれば眠れそうだし。
注意書きには車・バイクの乗り入れ禁止とか、焚き火禁止とか書いてあるけど、寝泊り禁止とか寝袋の持込禁止とかは書いてないし。24時間開放してるなら夜中に立ち入っても文句は言われなさそうだし。
しっかし、ここが東京のど真ん中あたりだったら不況のご時世、公園を24時間開放なんかしていたらホームレスのダンボールハウスとかビニールテントとかがずら~っと並んじゃうぞ。上野公園がそうだったし、この前立ち寄った隅田川の畔の公園にもホームレスの住処が並んでたし。そこへ行くと千波湖の公園、24時間開放しているわりにはホームレスの小屋とかテントとかが全然見当たらないっぽいね~。水戸はまだまだ地域社会の秩序が保たれているってことかな?
そういうわけで次回は千波湖の畔で寝袋に包まって野宿にけてーい。「何処に泊まってるの?」と聞かれたら、「ホテル千波湖です」って答えることにするかい?
あ、でも当日雨降ったらどうすっかな~? ‥‥ま、い~か。その時はその時だ。
この前の稽古の時は水戸駅近くのマックに泊まったけど、今、家計がヤバい。ちょっとでも金を節約しようと思い、水戸の電波塔の近くに手頃なサークル型のベンチを見つけたんで、試しにそこで寝てみることにした。
だけど今どきのベンチはホームレスの寝転がり防止のためか、座席にでっぱりが多くて座ることは出来ても寝転がりにくい構造になってる。これって挑戦かよ、受けてやろうじゃん。と気張って寝転がってみたら、でっぱりが背中に当たってやっぱり痛い。試しに下にレインコートとか敷いて寝てみたら、少しは寝やすくなったけど、背中に刺激が加わるもんだからなかなか眠れない。ベンチの横を車がびゅんびゅん通り過ぎていく。ここで運転ミスった車がベンチに突っ込んできたら、あの世行きかもな~なんて思っていたら、周りが湿っぽくなって霧が出てきた。上を見ると、夜空に霧の塊がふわ~っと流れている。 辺りの景色もだんだん霧に包まれて、マジであの世に行ったような気分になってくる。
寝づらいベンチなので大通りにあるベンチに移動。座席が平べったくて寝っ転がれるベンチへ移動。さあこれで眠れるかなと思っていたら、だんだん寒くなってくるし、すぐ横の通りを暴走族のバイクがでけぇ音出して通り過ぎるしで、眠れない。
こんな所で何やってんだオレ? 素直にマックで寝ようっと。
そういうわけで結局、今回も駅近くのマックに泊まった。
やべぇぞ、マジで所持金が限界だぞ。次もマックに泊まったら、次の稽古は飲まず食わずでやることになりそうだぞ。
どうすっかな~~~~~~~~~?
考えた末に気がついた。
そうだ、水戸には千波湖があるじゃないか。あそこは公園になってるし、夏場過ぎた今なら蚊も出なさそうだし。
マックを出てから自転車で千波湖の畔を物色してみると、あちこちに手頃なベンチが置いてある。張り出されている注意書きを読んでみると、公園は一部施設を除き24時間利用可能とか書いてある。
あ、そう。んじゃ今度の稽古日はここで寝よっと。
寒くなってきたけど、寝袋に包まれば眠れそうだし。
注意書きには車・バイクの乗り入れ禁止とか、焚き火禁止とか書いてあるけど、寝泊り禁止とか寝袋の持込禁止とかは書いてないし。24時間開放してるなら夜中に立ち入っても文句は言われなさそうだし。
しっかし、ここが東京のど真ん中あたりだったら不況のご時世、公園を24時間開放なんかしていたらホームレスのダンボールハウスとかビニールテントとかがずら~っと並んじゃうぞ。上野公園がそうだったし、この前立ち寄った隅田川の畔の公園にもホームレスの住処が並んでたし。そこへ行くと千波湖の公園、24時間開放しているわりにはホームレスの小屋とかテントとかが全然見当たらないっぽいね~。水戸はまだまだ地域社会の秩序が保たれているってことかな?
そういうわけで次回は千波湖の畔で寝袋に包まって野宿にけてーい。「何処に泊まってるの?」と聞かれたら、「ホテル千波湖です」って答えることにするかい?
あ、でも当日雨降ったらどうすっかな~? ‥‥ま、い~か。その時はその時だ。
2010年10月15日
10月9日の日記~キミトジャグジー公演「リライト」観劇
お仕事でトラブル発生。派遣社員でやってる本業でじゃなくて、ちまちまお小遣い稼いでる副業のほうだけど、状況ヤバいので法的に動くことにけてーい! これからお医者さんの診断書もらったり内容証明郵便書いたりと手間が増えそーだ。
ストレスのせいか、なんか記憶があちこちぶっ飛び始めたっぽいけど、リハビリのつもりで日記つけておこうっと。
10月9日
今日はキミトジャグジーの公演日、『リライト』って劇を上演するんだけど、まともに交通費払ったらそもチケット代も給料日までの食費も確実にぶっ飛ぶんで、水戸まで自転車で行くことに決めていたら、今日は本降りの雨かよ‥‥。もとから気分低調だしもうこのまま寝てよーかというくらいげんなりしたけど、
「たたが雨じゃねぇか!」
と思い直して、自転車で走り始めたらひでぇ目に遭った。水戸まで5時間半かけて走ったらレインコートに雨が染み込んでずぶ濡れと変わんねぇ。仕方ねぇから濡れた服のまんまで芝居観たよ。
んで、肝心の芝居の話だ。キミトジャグジー第12回公演「リライト」。
ヒロインはオタッキーな科学者が大切にしていたアンドロイドの女の子で~す。
あ、どっかで見たよな聞いたような設定。これって去年の水戸演劇フェスティバルでも上演された『ココロ』とかぶってないかい? ほら『ココロ』だよ『ココロ』。いかにもオタク受け狙ってますってか、オタクの心を虜にしますってか、オタクのお客さんぜひぜひ観に来てくださいなって感じでPRしてたあのお芝居だよ。実わオレ、『ココロ』をムチャクチャ観たかったんだよ~!! ポスターやフライヤーに描かれてた、リボンつけたミニスカの女の子に、くらぁ~~~~~っ、ときちまってさ~。
んだけど、チケット買いに行った時には全部売り切れてやんの。
「ぢぐじょーっ!! 買い占めたのはどこのオタク野郎だよっ!!」(自分はどうなんだ?)
「ざけんじゃねぇーっ!! オレをココロちゃんに会わせろーっ!!」
あの時はマジ、心で叫んじまったよ。あれはちょうど、オレが去年の水戸演劇学校に通っていた時のことだ。で、舞台のココロちゃんと会えなかったオレは、「ココロちゃんに会いたいよ~!」と心の中で叫びながら、相変わらずリハーサル室でゴリラみたいなのと顔突き合わせて‥‥あ、いいえ、何でもないです。真面目にお稽古してましたです。
で、『ココロ』と同じくアンドロイドの女の子をウリにしちゃってるみたいな『リライト』だけど、フライヤーに描かれてんのはケムール人がスカートはいたような人間モドキみたいなよく分かんないキャラ。なんなんじゃこりゃ~? こういうのとはあまりお近づきになりたくないな~とか思いつつも、オレは会場へ足を運んだわけだ。
で、物語の導入部、アンドロイドの女の子が登場したシーンで思っちまった。
「なんかこのストーリー、『ココロ』にケンカ売ってないか?」
ネタがネタなんだよ、「ショートケーキが好き」辺りはいいとしても、アンドロイドの魔改造で特殊機能付けちゃうとかおいおい客席の最前列じゃ小学生が観てるんだぞ親子連れで2人も来てるんだぞ等身大フィギュアなんて言葉使うなようわスカートに露骨に手を手を伸ばしてめくったりすんなよ~小学生が真似したらどうすんだよオタクになってフィギュア集めちゃったりしちゃったらどうすんだよ~。ってかこんなにどっさりシモネタ持ち込んじゃってやっぱりココロにケンカ売ってんのかな~これ? そのうち「ココロシステムがどうのこうの」なんてセリフまで飛び出してきて、
「や~っぱりこのストーリー、『ココロ』にケンカ売ってないか?」
と、思ってたら。
‥‥あ、アンドロイドの女の子に心が吹き込まれた。
その瞬間、世界がぶっ飛んだ。
全てが真っ白になった。
一生消えない思い出をありがとう。ありがとう。ありがとう。
ぶはははははははははははははははっ!! 大爆笑だよ大爆笑。こりゃ、ココロにケンカ売ってるなんてもんじゃねぇ、ココロをぶん殴ってケリ入れてヤキ入れちゃってスマキにして川に放り込んじゃうような、超ぶっ飛びすぎな展開、うわ何とかしてくれぇ笑いが止まらねぇ、あひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ!!。
今でもあの場面を思い出すと、心が真っ白にホワイトアウトします。
ここはどこ? わたしはだれ?
あ~何がなんだかよく分かんなくなってきてしまいました、カキコしてる本人も何書いてるんだかよく分かりません。脳ミソ暴走してるっぽいです、最近ストレスたまりまくりなもんでなおさらっぽいですね~。お脳をメルトダウン‥‥じゃねぇ、クールダウンします。
あ、でも。これ読んでキミトジャグジーにちょっとでも関心を持ってくれた人のために書いておきますが。
前半のおバカっぷりとはうって変わって、後半の展開はシリアスなタッチで魅せてくれます。
特にラストシーンへと至る最後の数分間の印象は強烈です。
アンドロイドの女の子の最後のセリフ、じ~んときました。
これからも時々、あの最後のシーンを思い出して、切ない気持ちになるんじゃないかと思います。
正直言って、どうしたらこんな凄いストーリーが作れるんだと思いました。
もしかするとこれからも、再演することがあるかもしれませんので、「観てもいいかな?」と興味を持たれた方は是非、観に行ってみてください。オススメです。
オレ的には、「ココロは観られなかったけどリライト観られたからよかったよかった~☆」みたいな。いや本気でそう思ってます。でもやっぱり『ココロ』も観たいかな~。
ストレスのせいか、なんか記憶があちこちぶっ飛び始めたっぽいけど、リハビリのつもりで日記つけておこうっと。
10月9日
今日はキミトジャグジーの公演日、『リライト』って劇を上演するんだけど、まともに交通費払ったらそもチケット代も給料日までの食費も確実にぶっ飛ぶんで、水戸まで自転車で行くことに決めていたら、今日は本降りの雨かよ‥‥。もとから気分低調だしもうこのまま寝てよーかというくらいげんなりしたけど、
「たたが雨じゃねぇか!」
と思い直して、自転車で走り始めたらひでぇ目に遭った。水戸まで5時間半かけて走ったらレインコートに雨が染み込んでずぶ濡れと変わんねぇ。仕方ねぇから濡れた服のまんまで芝居観たよ。
んで、肝心の芝居の話だ。キミトジャグジー第12回公演「リライト」。
ヒロインはオタッキーな科学者が大切にしていたアンドロイドの女の子で~す。
あ、どっかで見たよな聞いたような設定。これって去年の水戸演劇フェスティバルでも上演された『ココロ』とかぶってないかい? ほら『ココロ』だよ『ココロ』。いかにもオタク受け狙ってますってか、オタクの心を虜にしますってか、オタクのお客さんぜひぜひ観に来てくださいなって感じでPRしてたあのお芝居だよ。実わオレ、『ココロ』をムチャクチャ観たかったんだよ~!! ポスターやフライヤーに描かれてた、リボンつけたミニスカの女の子に、くらぁ~~~~~っ、ときちまってさ~。
んだけど、チケット買いに行った時には全部売り切れてやんの。
「ぢぐじょーっ!! 買い占めたのはどこのオタク野郎だよっ!!」(自分はどうなんだ?)
「ざけんじゃねぇーっ!! オレをココロちゃんに会わせろーっ!!」
あの時はマジ、心で叫んじまったよ。あれはちょうど、オレが去年の水戸演劇学校に通っていた時のことだ。で、舞台のココロちゃんと会えなかったオレは、「ココロちゃんに会いたいよ~!」と心の中で叫びながら、相変わらずリハーサル室でゴリラみたいなのと顔突き合わせて‥‥あ、いいえ、何でもないです。真面目にお稽古してましたです。
で、『ココロ』と同じくアンドロイドの女の子をウリにしちゃってるみたいな『リライト』だけど、フライヤーに描かれてんのはケムール人がスカートはいたような人間モドキみたいなよく分かんないキャラ。なんなんじゃこりゃ~? こういうのとはあまりお近づきになりたくないな~とか思いつつも、オレは会場へ足を運んだわけだ。
で、物語の導入部、アンドロイドの女の子が登場したシーンで思っちまった。
「なんかこのストーリー、『ココロ』にケンカ売ってないか?」
ネタがネタなんだよ、「ショートケーキが好き」辺りはいいとしても、アンドロイドの魔改造で特殊機能付けちゃうとかおいおい客席の最前列じゃ小学生が観てるんだぞ親子連れで2人も来てるんだぞ等身大フィギュアなんて言葉使うなようわスカートに露骨に手を手を伸ばしてめくったりすんなよ~小学生が真似したらどうすんだよオタクになってフィギュア集めちゃったりしちゃったらどうすんだよ~。ってかこんなにどっさりシモネタ持ち込んじゃってやっぱりココロにケンカ売ってんのかな~これ? そのうち「ココロシステムがどうのこうの」なんてセリフまで飛び出してきて、
「や~っぱりこのストーリー、『ココロ』にケンカ売ってないか?」
と、思ってたら。
‥‥あ、アンドロイドの女の子に心が吹き込まれた。
その瞬間、世界がぶっ飛んだ。
全てが真っ白になった。
一生消えない思い出をありがとう。ありがとう。ありがとう。
ぶはははははははははははははははっ!! 大爆笑だよ大爆笑。こりゃ、ココロにケンカ売ってるなんてもんじゃねぇ、ココロをぶん殴ってケリ入れてヤキ入れちゃってスマキにして川に放り込んじゃうような、超ぶっ飛びすぎな展開、うわ何とかしてくれぇ笑いが止まらねぇ、あひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃひゃ!!。
今でもあの場面を思い出すと、心が真っ白にホワイトアウトします。
ここはどこ? わたしはだれ?
あ~何がなんだかよく分かんなくなってきてしまいました、カキコしてる本人も何書いてるんだかよく分かりません。脳ミソ暴走してるっぽいです、最近ストレスたまりまくりなもんでなおさらっぽいですね~。お脳をメルトダウン‥‥じゃねぇ、クールダウンします。
あ、でも。これ読んでキミトジャグジーにちょっとでも関心を持ってくれた人のために書いておきますが。
前半のおバカっぷりとはうって変わって、後半の展開はシリアスなタッチで魅せてくれます。
特にラストシーンへと至る最後の数分間の印象は強烈です。
アンドロイドの女の子の最後のセリフ、じ~んときました。
これからも時々、あの最後のシーンを思い出して、切ない気持ちになるんじゃないかと思います。
正直言って、どうしたらこんな凄いストーリーが作れるんだと思いました。
もしかするとこれからも、再演することがあるかもしれませんので、「観てもいいかな?」と興味を持たれた方は是非、観に行ってみてください。オススメです。
オレ的には、「ココロは観られなかったけどリライト観られたからよかったよかった~☆」みたいな。いや本気でそう思ってます。でもやっぱり『ココロ』も観たいかな~。